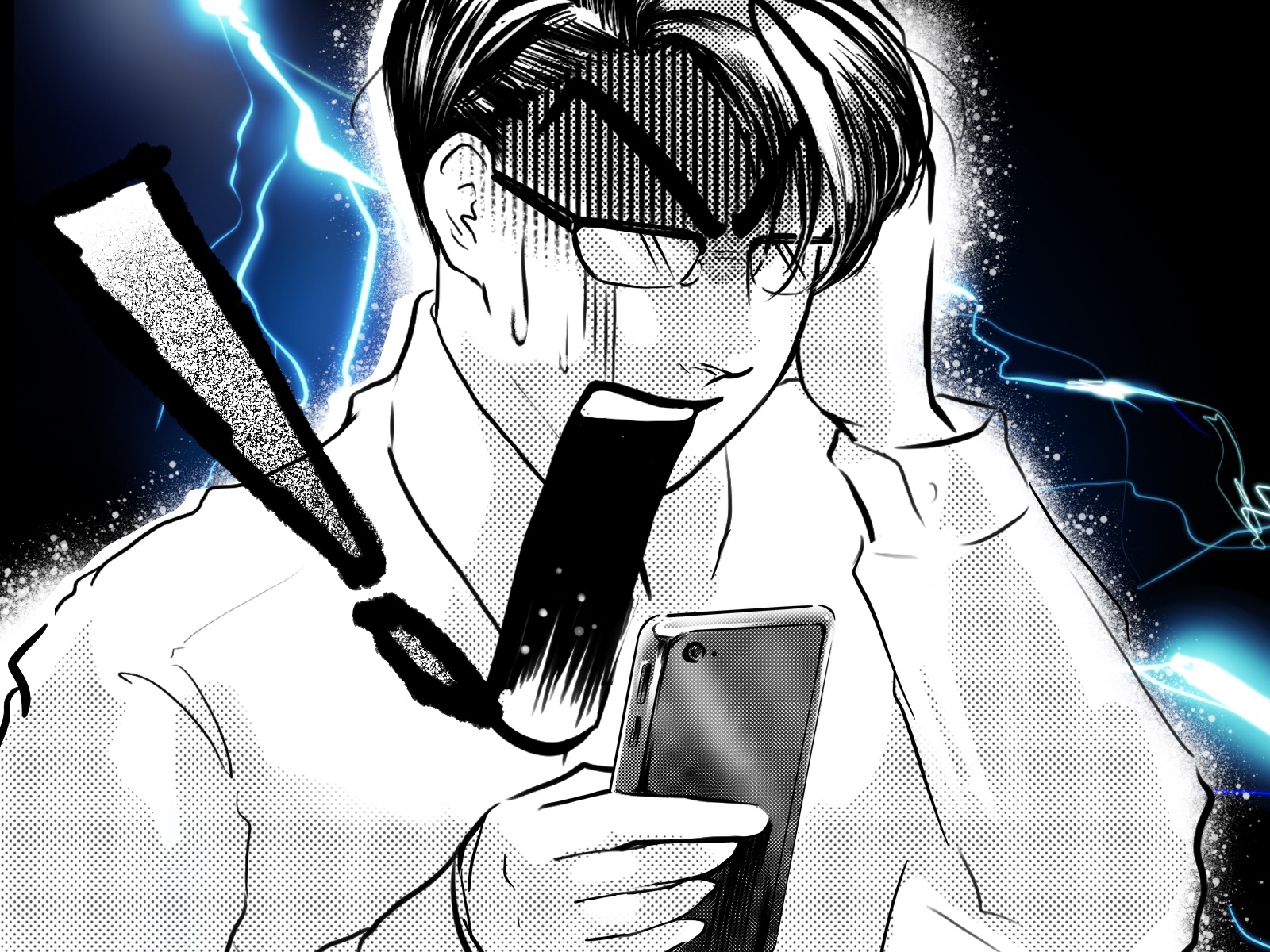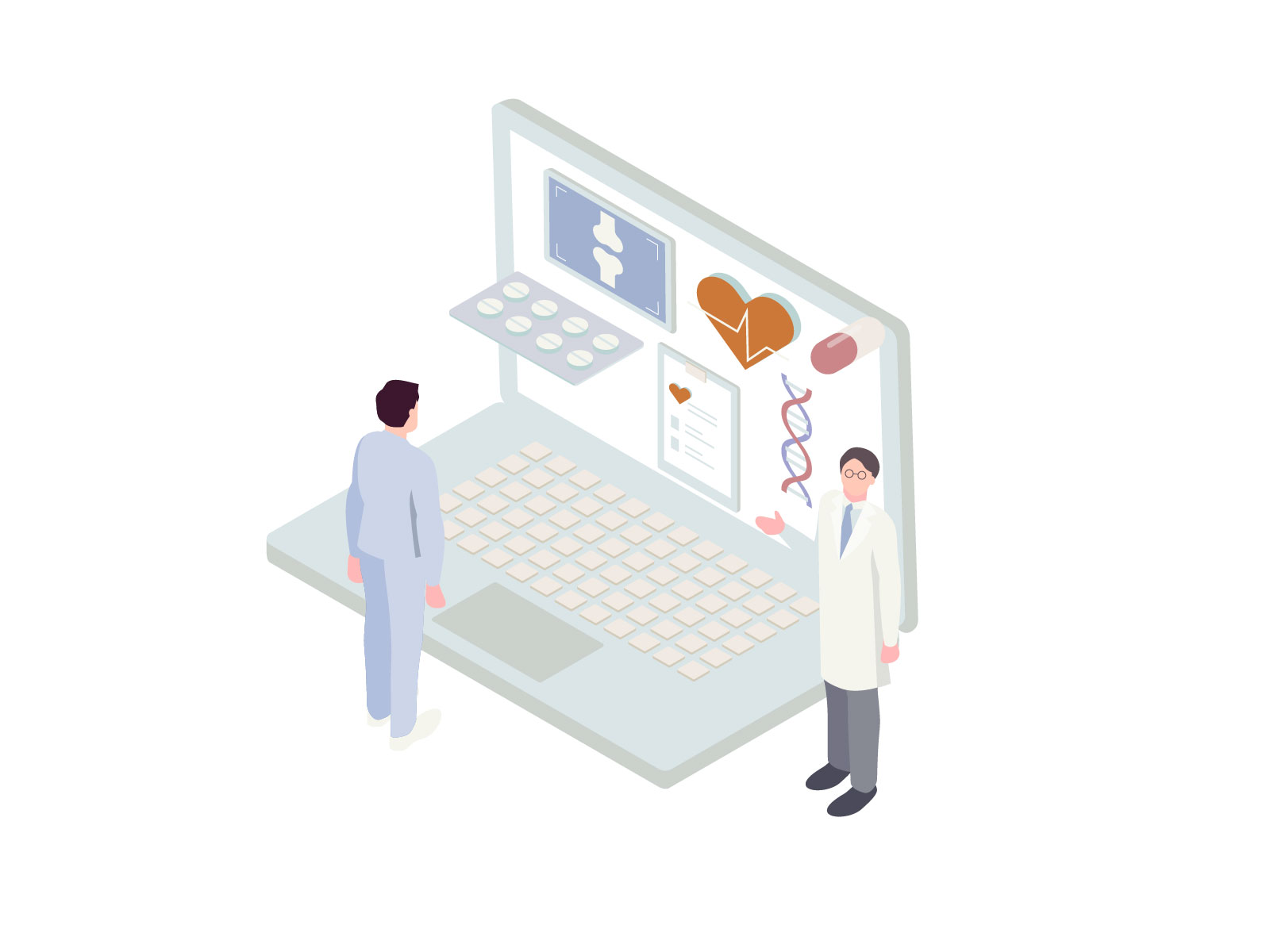元気に見えたあの日のあとで―介護認定の落とし穴と家族ができること
番号 106

調査日と生活実態の差を埋める視点
先日ニュースで「介護認定の結果が実態より軽く出て家族が戸惑っている」という特集を見ました。
転倒や物忘れが続いているのに、調査当日は受け答えがしっかりしていたため想定より軽い区分になったという内容だったそうです。
以前、母も認知症の症状がひどくなり、日常生活のトラブルが連発した為、認定調査に来た調査員に「私は何でも一人でやれています!!」と急にハキハキしゃべり、"元気認定"を頂くという不本意な過去を思い出しました。
介護認定は、訪問調査、主治医意見書、審査会を経て決まる仕組みだと言われています。
判定基準は病名ではなく、「日常生活にどれだけ介助の時間が必要か」だそうです。
厚生労働省の公表資料では、要介護・要支援認定者は約700万人にのぼると言われています。制度は全国共通の基準で運用されているとされています。
一方で、老年心理学の研究では、高齢者は自尊心や自立心を守ろうとして、自分の困難を過小評価する傾向があると報告されているそうです。
いわゆる“取り繕い”が起きやすいと言われています。特に初対面の調査員に対しては、「まだできます」と答える割合が高いという調査結果もあるそうです。
問題は、制度の欠陥というよりも “取り繕い”と“限られた調査時間”が重なる点だと言われています。
本来は日常の連続性で判断される制度が、その日の印象に影響を受けやすくなる可能性があるのだそうです。

取り繕いと「できる」と「危ない」のあいだにあるもの
「今日は大丈夫」「まだまだ自分でできるよ」
そう言って背筋を伸ばす親の姿に、安心しながらも、どこか胸に引っかかるものを感じたことがある介護家族は多いのではないでしょうか?
公的サービスの利用につながる要介護認定では、市区町村の調査員が自宅を訪れ、心身の状態を確認します。つまり、限られた時間の印象が、その後の支援量に影響する可能性があるのです。
問題になりやすいのが、本人の「取り繕い」です。高齢者心理の研究では、自尊感情を保とうとする働きが強く、他者評価の場面では「できないこと」よりも「できること」を示そうとする傾向があるとされています。加えて、医療現場などでも見られるように、評価の場では一時的に能力が高く発揮されることがあるとも報告されています。
さらに、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)は、時間帯や環境によって大きく変動します。午前中は比較的安定していても、夕方になると混乱が強まる。家族が隣にいればできるが、一人では難しい――こうした日々の揺らぎは、短時間の面談では見えにくいものです。その結果、生活実態とのギャップが生まれることがあります。
「元気に見えたのだからよかった」と思いたい気持ちは自然です。しかし、その安心感が、後に「思ったより支援が足りない」という現実につながることもあります。大切なのは、親の言葉を否定することではなく、暮らし全体をどう共有するかという視点なのです。

認定の仕組みと調査員の視点――限られた時間で何を見ているのか
要介護認定は、全国共通の基準に基づいて行われます。まず、訪問調査によって心身の状態や日常生活の様子が確認され、その結果をもとに「一次判定」(コンピュータ判定)が行われます。
その後、医師の意見書なども踏まえ、介護認定審査会による二次判定が行われ、最終的な区分が決定されます。
調査員は、決して一部だけを見ているわけではありません。身体機能、認知機能、生活動作、問題行動の有無など、多岐にわたる項目を確認しています。ただし、評価はあくまで客観的な基準に沿って進められるという点が重要です。例えば、「食事が自立しているか」という項目では、“自分で口に運べるかどうか”が中心的な判断材料になります。「声をかけ続けなければ始められない」といった背景事情は、補足情報として扱われることが多いのです。
また、調査は通常1時間前後という限られた時間で行われます。調査員は、その時間内でできるだけ正確に状況を把握しようとしますが、一日の変動や長期的な経過までは直接確認できないという制約があります。さらに、本人の発言が明確であればあるほど、それが判断材料として重視される傾向もあります。
つまり、仕組みは公平性を重視して設計されていますが、生活の細かなニュアンスまですべて自動的に反映されるわけではないのです。この構造を理解することが、家族の次の一歩につながります。

“あの日”にすべてを託さないために―家族ができる備え
では、家族として何ができるのでしょうか。大切なのは、調査の日だけに頼らない準備です。
第一に、日常の具体的なエピソードを記録しておくことです。「物忘れがある」ではなく、「週に何回、同じ質問を繰り返す」「買い物で同じ物を複数購入してしまう」など、頻度や状況を整理します。こうした具体性は、調査員にとっても状況を理解する手がかりになります。
第二に、同席して補足する姿勢です。本人が「できます」と答えた場合でも、「見守りがあれば可能」「時間をかければできる」といった実情を穏やかに伝えることが重要です。これは否定ではなく、支援を適切につなぐための情報共有です。
そして第三に、結果が生活実態と大きく異なると感じた場合には、相談や見直しの機会があることを知っておくことです。状態の変化に応じた区分変更申請など、制度には再評価の仕組みが用意されています。「間違いを正す」というよりも、「より実態に近づけるための相談」と捉えるほうが現実的でしょう。
介護は一日で終わるものではありません。だからこそ、あの日の印象だけにすべてを委ねるのではなく、日々の積み重ねを丁寧に伝えていくことが大切です。暮らしのリアルを言葉にし、準備を整えることから始めてみてはいかがでしょうか。

その他のコラム
もっと見る