高齢者宅を狙う訪問販売業者の“下見行動・マーキング”とは
番号 71

一度狙われたら付けられる‟マーキング”
先日、やたら訪問販売の業者が来る高齢者夫婦が住むお宅に記された‟マーキング“というニュースを見ました。
マーキングとは空き巣や訪問販売業者間で交換される住人の属性を知らせる記号、マークのことでポストや表札、ガスメーターなど目立たない所に暗号のように書かれているといいます。
そのお宅ではガスメーターの下側に「MWロ◎」と書かれていたそうで、恐らくMは男性、Wは女性、ロは老人、◎は契約簡単といった意味ではないかと推測します。
こうしたマーキングによるローマ字、記号例は高齢者だけでなく、20代(20)、家族(F)、留守時間8:00-19:00(8-19)など属性ごとに細かく分かれて記載され識別されていると見られます。
恐ろしくアナログな手法ではあるものの、シンプルで誰にでも理解できる確実な方法であるため、闇バイトのような特別なトレーニングを受けていない営業マンでも簡単かつ確度高く営業活動を行っているといいます。
「高齢者夫婦」や「高齢者の一人暮らし」、「認知症あり」、「この時間はデイサービスに行っていて不在」など犯罪につなぎやすいような情報がいくつも存在するため、特に家族が遠く離れているような場合は近隣にも声をかけて対策することが肝要だと考えます。
また、「近所に知り合いがいない」「近所づきあいをほとんどしていない」といった状況でも必ず地域には民生委員や認知症サポーターといったボランティアで見守りなどを行う方や団体が存在していますので、市区町村やお近くの地域包括ケアセンターへ相談することをお勧めします。

なぜ下見が行われるのか?
まず、訪問販売業者(あるいは悪質業者)が“下見”を試みる背景を押さえておくことで、警戒すべき行動に気づきやすくなります。
1. 判断材料を得るため
下見は、相手先の住人が応対してくれるかどうか、在宅時間帯、構造・出入り口の位置・死角・周囲の見通し、庭や建具の状態などを把握するために行われるとされています。
たとえば、「この家は応対してくれる」「部材を持ち込んで工事できそうだ」「敷地に足場を掛けられる場所があるか」などを推定したいからです。
2. 留守かどうかを確認するため
インターホンや呼び鈴を鳴らして反応を見たり、屋外で様子をうかがったりする行為は「この家が留守になる時間帯を掴む」ための典型的な手法とされています。
実際、警察庁の調査では、空き巣が留守を確認する手法として「インターホンを押す」が 45.7% を占めるという報告もあります。
3. 話をさせて態度・情報を引き出すため
一見「点検」「調査」「アンケート」を装って訪問し、応対者の関心・警戒心・生活サイクルなどを探ろうとする場合があります。
応答の仕方で、相手の認知力・疑念度といった“心理傾向”を把握しようとすることも考えられます。
こうした目的を理解しておけば、「訪問者が何回も来る」「近づき方が不自然だ」「質問の角度が探るようだ」といった行動に敏感になれます。

チェックすべき下見らしき行動・兆候
ここでは、高齢者(またはそのご家族)が日頃から気をつけたい、訪問業者による下見行動と思われる兆候を、具体的な視点で整理します。
ただし、これらはあくまで「警戒すべき可能性のある行動」であり、必ずしも下見であるとは断定できません。
そのため過度に疑心暗鬼になるのではなく、バランスをとりながら「違和感の累積」があれば注意を強める判断を心がけることが重要だといえます。
●チェックポイント 1:複数回・時間帯を変えて来訪する
同じ人物や車を、異なる時間帯・別の日に見かける。特に午前・昼間・夕方など時間帯を変えて様子をうかがっています。
1回ではなく、2〜4回程度、複数回にわたって接近してくる傾向があるという防犯関係者の見方もあります。
朝・昼・夕と時間帯を変えて来る訪問者は要注意であり、日中留守かを探っている可能性があります。
●チェックポイント 2:インターホン/呼び鈴を使う・押してすぐ退く
呼鈴を押して反応を待たずにすぐ立ち去る、という行動。「応対がないなら留守と判断したい」可能性があります。
呼鈴を押し、応答があるかどうか・戸口まで来るかどうかを見ている。応答者の数・構え方・応答態度を観察するためという指摘があります。
●チェックポイント 3:正体をぼかした名乗り・説明の曖昧さ
「点検に来ました」「調べに来ました」など具体性を持たない説明で訪問し、正体を明示しない。
公共機関・会社を名乗るが、事前通知がない、名刺や証明書を提示しない。
これについては、訪問販売に関するルールとして、訪問前に事業者が名乗る義務や目的説明義務が定められています。
●チェックポイント 4:敷地内に出入りする、近づいて観察する
花壇・物置・植木など近づきやすい位置を探るように歩く/停滞する。
敷地内(外構部分)に入り込んでまで観察する、門扉・フェンスの隙間をのぞき込む。
携帯電話を操作しながら地図を見たり写真を撮ったりする動き。これらは“記録”を残して調査する動きと見なされることがあります。
●チェックポイント 5:不審な車両・停車行為
家の近くに知らない車や見慣れない車が頻繁に停まっている。
車の窓からモニタリングするような態度(車内でスマホを見ながらじっとしているなど)。
車を停めて近隣をうろついたり、移動しながら家の外観を確認しているような雰囲気。
●チェックポイント 6:質問・話題が探る内容である
家の構造(例:玄関の位置、裏口の有無、窓の配置)を聞こうとする。
日常の生活パターン(「普段、お留守の時間はありますか?」など)を尋ねる。
他の住人や来客、訪問業者などの頻度を聞くような話題を振る。
過度に興味を引き出すような話しかけ方をして、情報を引き出そうとする傾向。
●チェックポイント 7:その他の違和感・異変
郵便受けやポストにチラシ・紙片・印が繰り返し貼られている。
玄関まわり、表札、宅配箱、ドア近辺に汚れ・印跡・貼り紙など見慣れない物がある。
近隣住人が「あの人、何度も見かけた」と言っている。
いつもとは違う服装や作業着を着た人物が通行している。
まれに、犬の散歩や通りすがりを装った人が立ち止まって方向転換したり、同じ場所を行き来したりする。
これら複数の要因が重なれば、「この人はただの業者ではなさそうだ」という直感をもつことができます。高齢者自身で判断するのが難しい場合は、家族や地域に相談することが大切です。
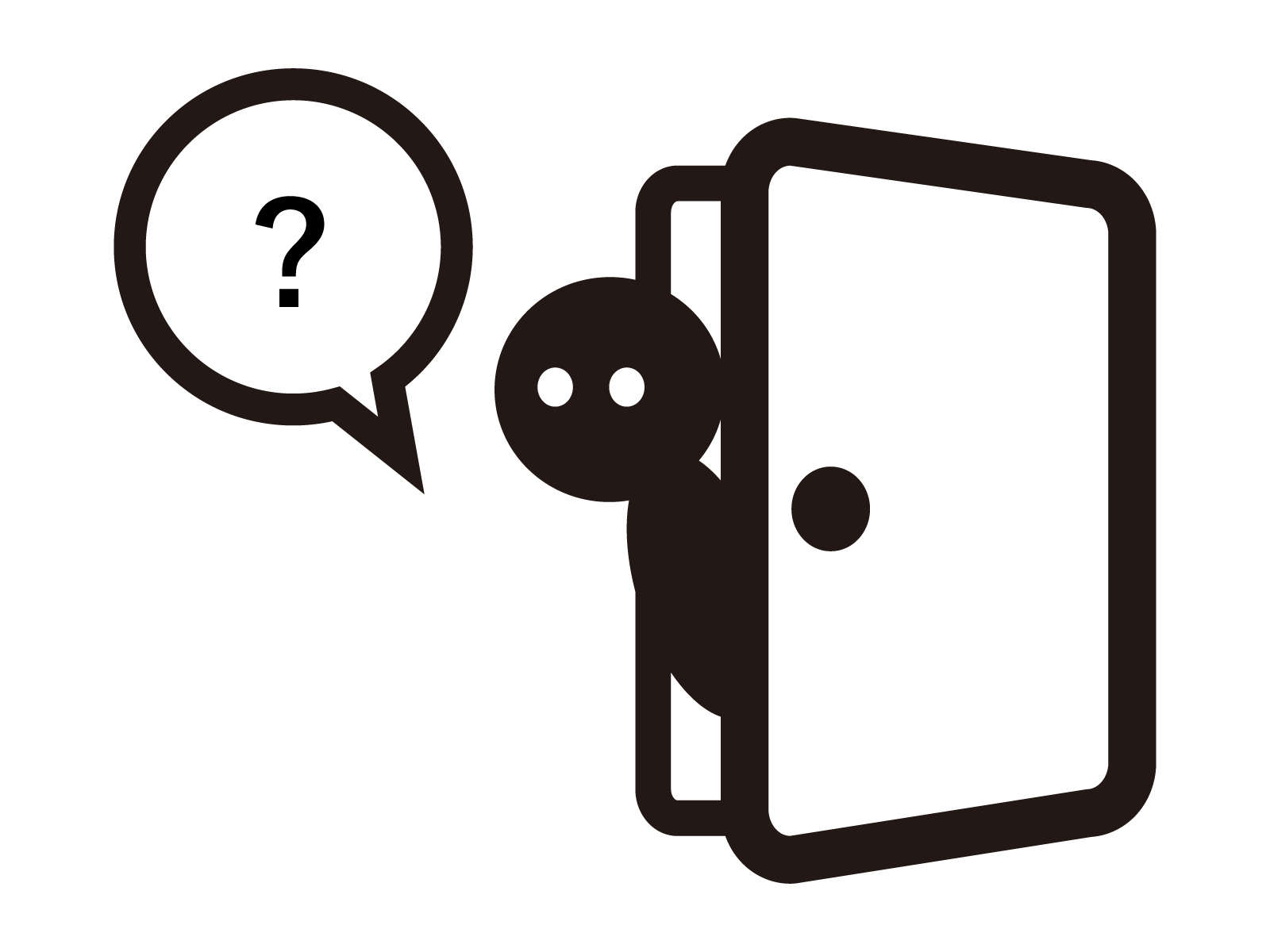
訪問販売業者のマーキングや下見行動を見つけたときの対処方法
訪問販売業者の中には、販売のためではなく、ターゲットを絞る目的で不審な行動をとる者がいると報告されています。
たとえば、家の様子を確認したり、ポストやメーター付近に小さなシールや印を付けたりするなどです。
こうした行為を見つけたときは、冷静かつ適切に対処することが重要です。
1. まずは慌てずに安全を確保します
不審なマーキングや人物を見つけても、直接注意したり問いただしたりすることは避けましょう。相手がどのような人物かわからないため、刺激してトラブルになるおそれがあります。まずは、玄関や窓をしっかり施錠し、屋外に出ずに室内から安全を確保してください。
2. 記録を残します
発見した印や物の状態を、スマートフォンなどで写真に撮っておきましょう。撮影する際は、できるだけ近づかずに安全な場所から撮影します。
また、不審な訪問者を目撃した場合は、特徴(性別・年齢・服装・持ち物・車の色やナンバーなど)をメモしておくことが後の確認に役立ちます。
3. 自分で消さずに警察に相談します
印やマーキングを見つけても、自分ではすぐに消さず、まず警察へ相談することが有効です。
証拠が残っている状態で連絡することで、警察が防犯パトロールを強化したり、調査につなげたりできるためです。
警察への通報は、緊急時は110番、緊急性が低い場合は最寄りの交番や警察相談専用電話「#9110」を利用するとよいでしょう。
4. 管理者や家族にも連絡します
集合住宅や賃貸住宅では、管理会社や大家さんにも知らせましょう。建物全体での注意喚起や防犯対策がしやすくなります。
一人暮らしの方は特に、家族や近所の人に早めに報告し、情報を共有することが安心につながります。
5. 周囲の人と連携します
不審な行為は、地域全体で気づき合い、声を掛け合うことで抑止効果が高まります。
町内会や自治体の防犯ネットワーク、防犯メールなどを活用し、近隣の人々に情報を伝えましょう。
6. 再発を防ぐためにできること
マーキングや下見の被害を防ぐためには、普段から以下のような予防策を行うことが有効です。
• 玄関や庭先、メーター周りを定期的に点検する
• 郵便受けやドアに貼られたチラシや紙片をためずに取り除く
• 防犯カメラやセンサーライトを設置し、「録画中」などのステッカーを掲示する
• 訪問者には必ず身分証明書の提示を求め、ドアをすぐに開けない
実家に最近やたら訪問販売業者が訪ねてくると感じた時は、一度家の周りのマーキングをチェックしてみてはいかがでしょうか?

その他のコラム
もっと見る











