"定期巡回・随時対応型訪問介護看護"は持続可能なサービスなのか?
番号 66

過酷すぎる勤務実態
先日、あるテレビ番組で『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』の事業所を特集した番組を見ました。
『定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回サービス)』とは要介護者が住み慣れた自宅で自立した日常生活を送れるよう、24時間365日体制で介護と看護をサポートするサービスとして2012年からスタートした公的介護保険が利用できる制度です。
高齢者の在宅介護のニーズの高まりを背景に全国で事業所数も増加中で、厚生労働省の最新の報告によると看護師がいる「一体型」看護師がいない「連携型」令和4年度の事業所数が1,255か所となるそうです。
また、サービス内容としては定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を行うとともに、看護師等による療養上の世話や診療の補助を行うもの(訪問看護を一体的に行う場合)とされており、「一体型」と「連携型」や住む地域のカバー範囲にもよりますが、利用料は1割負担で月に数万円程度の"サブスク"で利用できるという、利用者や介護家族にとっても至り尽くせりの‟神制度“であることは間違いないでしょう。
しかしながら、そのテレビ番組で特集された事業者は自らも看護師の資格を有し、数人の限られた人員と共に日中と夜間を3交代で回しており、職員が体調不良で急な休みになってしまった場合は、12時間以上の代替勤務になってしまう事もままあるといいます。
精神的にも、人数的にもギリギリの職員で日中夜問わず対応し、回数制限がないことをいい事に「寂しい」や「不安だから」といった本来の目的から外れた呼び出しなども往々にされることから、十分な睡眠や休憩など取ることもままならず案の定、職員の定着率は低下の一途を辿っているとのことでした。
『2025年問題』を迎えた今、さらに需要が高まり、ますます必要とされている制度である一方、一般企業では到底考えられない労働条件のこの事業モデルは果たして持続可能なのか?そこには、職員や事業経営者の事業者側が只々痛みに耐える、ガマン比べのような過酷な現状が見え隠れしていました。

「こうなることは容易に想像つく」持続可能性の欠如
見てきたように定期巡回サービスの持続可能性の欠如は、日本の高齢者介護システムが直面する最も深刻な構造的課題の一つとして浮上しています。
財政的持続可能性の危機は、多層的かつ根本的な問題を内包しています。
まず、現行の介護報酬体系は、このサービスモデルの複雑性と高度な専門性を適切に評価できていません。
例えば、24時間対応や複数の専門職による包括的ケアに要する実際のコストと、現行の報酬単価との間には深刻なギャップが存在します。
多くの事業者は、サービス提供に必要な人件費や運営コストを、現行の月額定額制の介護報酬モデルでは到底賄えない状況に直面しています。
厚生労働省の調査によれば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の約60%が経営的に厳しい状況にあり、赤字運営を強いられています。
特に、都市部以外の地域では、この傾向がさらに顕著となっており、サービスの地域間格差が拡大しているといいます。
次に、人的資源の持続可能性においても、危機的状況が続いています。
介護職員の平均年齢は年々上昇し、若年層の新規参入は著しく減少しています。
介護現場の過酷な労働環境– 低賃金、身体的・精神的負担、社会的評価の低さ – が、人材確保を根本的に阻害しています。
具体的には、介護職の平均年収は全職種平均と比較して約20%低く、離職率も約16%と、他産業と比較して非常に高い水準にあるといわれています。
他にもサービス品質の維持ついても、これらの構造的課題によってさらに困難になってきています。
慢性的な人材不足と財政的制約により、利用者一人ひとりのニーズに応じた柔軟で質の高いケアの提供が事実上不可能となっています。
慢性的な人員不足の為、職員の体調が悪くても代替がきかず、「多少の熱なら・・」と無理して出勤し、高齢者へ感染症を蔓延させてしまうようなとてつもないリスクを抱えた上、仮に休めたとしても代替要員が出勤シフトを継続してしまい、労働基準法の上限時間を大幅に超えてしまうような事態も起きかねません。
悪循環となった事業所は、高齢者の多様で複雑なニーズに適切に対応できず、たちまち画一的なサービス提供がでいなくなり、結果として利用者満足度の低下を招いてしまっています。
さらに、これらの課題は悪循環を形成し、サービスの持続可能性をさらに脅かしています。
財政的制約は人材確保を困難にし、人材不足はサービス品質の低下を引き起こし、サービス品質の低下は利用者数の減少と事業者の経営悪化につながるという負のスパイラルが顕在化しています。
このような状況は、単なる一時的な課題ではなく、日本の介護システムの構造的な限界を示唆しており、事業者としても、事業を維持させる為にも無理を強いながら継続せざるを得ない状況が生まれいるのです。
高齢化が加速度的に進む中、現行のサービスモデルは根本的な再設計なしには持続不可能であり、制度設計、財政支援、人材育成における抜本的な改革が喫緊の課題となっています。
今後、この危機的状況を打開するためには、介護報酬の抜本的な見直し、介護職の社会的地位と待遇の改善、テクノロジーの活用による業務効率化、多職種連携の強化など、総合的かつ革新的なアプローチが不可欠となるでしょう。

限られた人数しか看れなくなる
課題解決に向けて、以下の多角的なアプローチが不可欠です。
第一に、制度改革が急務です。
現行の介護報酬体系を抜本的に見直し、24時間対応や包括的ケアの複雑性を適切に評価する必要があります。
具体的には、サービスの専門性と労働集約性に見合った報酬単価の設定、地域の実情に応じた柔軟な加算制度の導入が求められます。
第二に、新たなサービスモデルの開発が重要です。テクノロジーの戦略的活用により、サービスの効率性と質を同時に向上させる必要があります。
例えば、IoTデバイスや遠隔モニタリングシステムの導入により、限られた人的資源を最適化し、きめ細かなケアを実現できます。
AIを活用した予測的介護支援システムも、個別ニーズに応じたサービス提供を可能にするでしょう。
第三に、多職種連携の抜本的な強化が求められます。
医療・介護・福祉の専門職間で、よりシームレスな情報共有と協働体制を構築する必要があります。
デジタル連携プラットフォームの整備、共通研修プログラムの開発、専門職間の相互理解を促進する仕組みづくりが重要となります。
そして、何よりも重要だといえるのが、人材確保戦略です。
介護職の社会的地位向上、処遇改善、キャリアパスの明確化が不可欠です。具体的には、
- 基本給の引き上げ
- 継続的な教育・研修機会の提供
- メンタルヘルスサポート体制の整備
- キャリア段位制度の拡充
しかしながら、利用者や利用者の家族が個人的に変えられる所は少なく、要介護1以上になって慌てて探してみて初めて適性なサービスが受けれるかどうか?が分かる受動的な現象が起きています。
即効性のある解決策が期待できない以上、近くの事業所が持続不可能で閉めたり、統廃合されたりして昔から住んでいる一部の利用者のみ恩恵を受けるような事態になることも想定されます。
なかなか変わらない国の制度を待つのではなく、我々利用者側はどこの地域のサービスがより受けやすいか?介護に手厚く進んでいる自治体や地域はどこなのか?の情報を確認し、早くからその地に引っ越しをしたり、自身の住まいの地域で享受できる恩恵を確実に受けられるよう、ご自身の家族に限定した『パーソナル介護』に関する情報に日頃からアクセスしておくことが、極めて重要なのではないでしょうか?
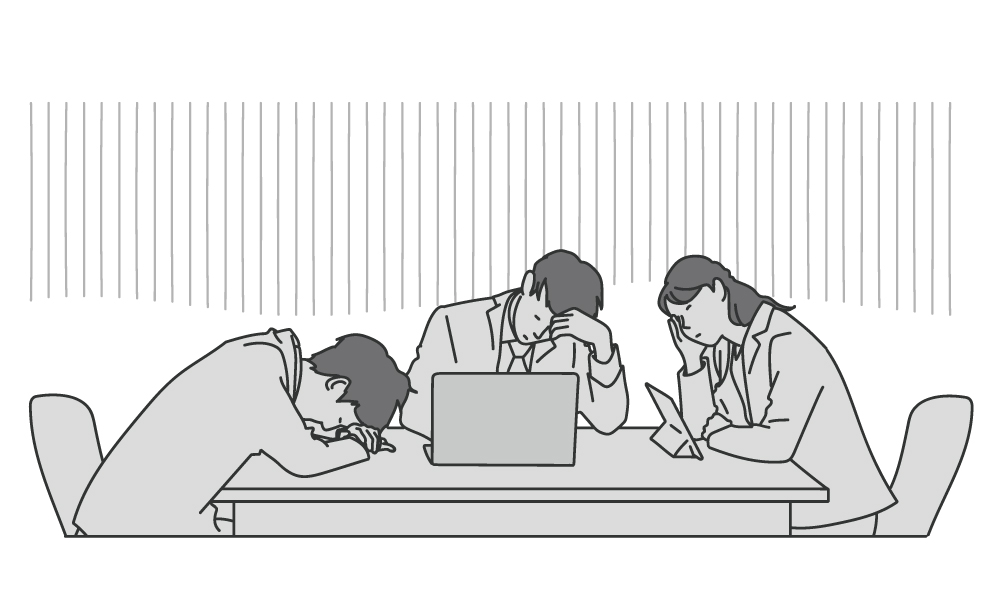
その他のコラム
もっと見る











