多くの認知症家族が抱える『もっと早く何かできていれば問題』
番号 64

認知症を悟られたくない親の“取りつくろい”が及ぼす影響
先日、アイトラッキング(視線計測)技術を用いて認知症の簡易診断を行う神経心理検査用プログラムのニュースを見ました。
タブレット端末にインストールしたアプリで画面に表示される質問に沿って被検者が正解の箇所を見つめることにより、データが自動的にスコア化され、定量的かつ検査者の知識や経験に依存せず客観的に評価することがなんと約3分で可能になるといいます。
先般承認され、大ニュースにもなった日本初の認知症治療薬も”初期“の認知症が適用になる為、かなり進んでしまってから専門医に受診しても処方されない可能性もあります。
また、簡易診断機器で疑いが出た後、病院の検査においても昨今はMRIの画像診断でもAIが用いられ、脳の萎縮による重症度分類も高精度で出す事ができ、怪しい段階で早く受診さえすれば、早く薬物治療に入れる事になり、その後の治療計画も立てやすくなるというメリットがあります。

このアイトラッキング以外にも昨今では沢山の簡易診断アプリが登場し、早期からケアに取り組めるご家庭が増えてきましたが、従来の診断プロセスには、以下のような本質的な制限がありました:
1. 限定的な評価ツール:
標準的な認知機能テストは、包括的な評価が難しく、初期の微細な変化を検出する能力に限界がありました。
2. 時間的制約:
医療従事者は限られた診察時間内で複雑な症状を評価しなければならず、詳細な分析が困難でした。
3. データ処理の限界:
人間の認知能力では、複雑な医療データを瞬時に分析し、関連性を見出すことが困難です。
これらの課題に対し、機械学習アルゴリズムは、膨大な医療データを瞬時に処理し、人間の目では気づきにくい微細なパターンや変化を検出できます。
このAI技術による診断の進化は、認知症の早期発見と適切な介入を大きく前進させる可能性を秘めており、単なる技術革新を超えて、患者の生活の質を向上させる重要な医療イノベーションとして期待されています。
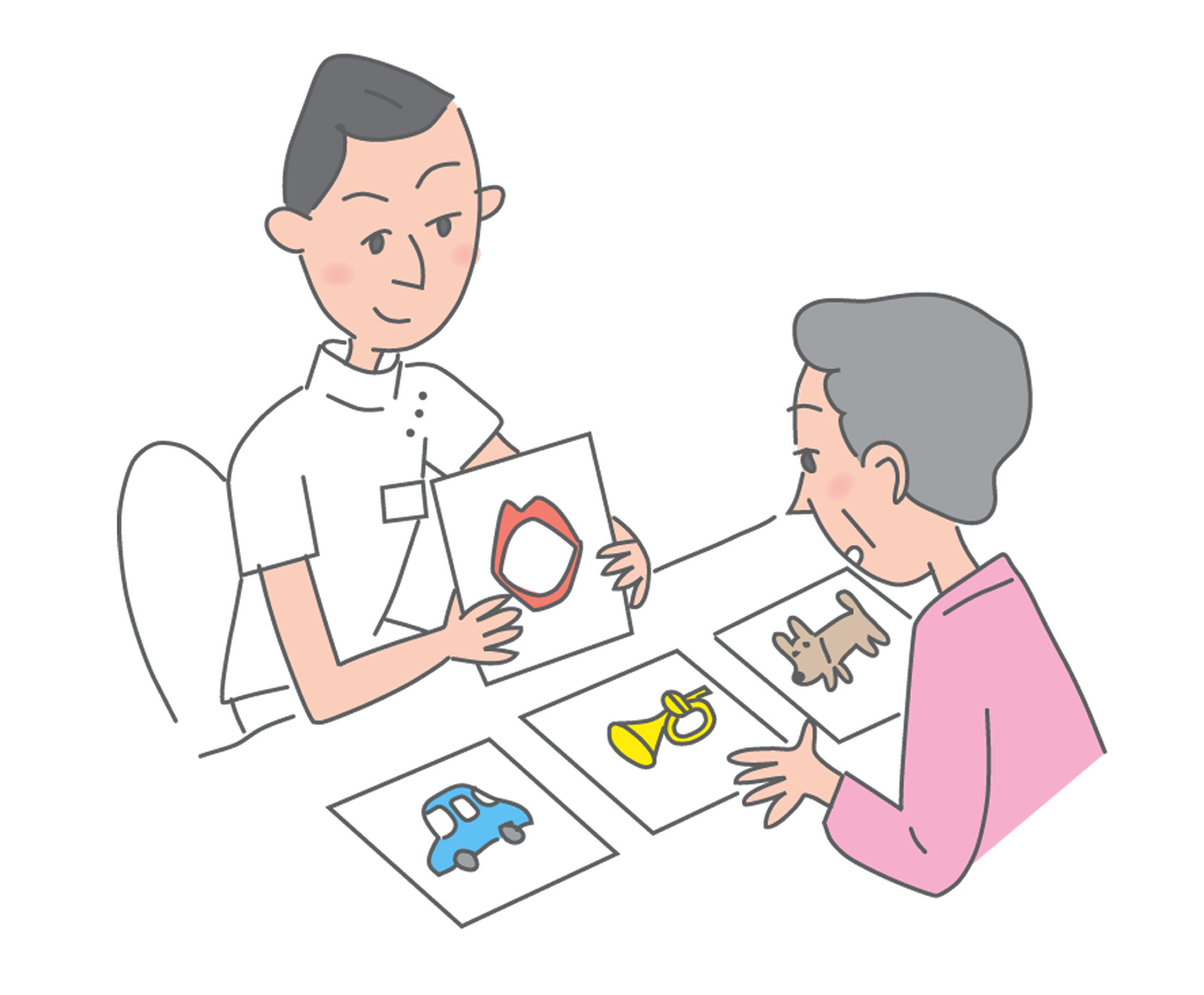
親も子もお互い知りたくない認知機能の低下
認知症初期の頃の母も、食パンを毎日1斤買ってきては冷凍庫に入れ、家族に見つかると「特売で安かったから・・」と特売値札のついていない普通のパンをひたすら買ってきたり、薬を飲み忘れていても「飲んだ」と言い張り、夕方一気に飲んで体調を崩したりと認知症初期に“取り繕い”が横行していました。
さらには介護レベルの調査に来た役所の職員さんの質問にはびっくりするぐらいハキハキ答え、やってもいない日常生活を、「いつも一人でやっています!」と堂々言い張り、“介助の必要なし”と評価されてしまったりと、認知症の親を持つ方ならばこの“取り繕いあるある“はお馴染みのエピソードではないしょうか?
「いつも通い慣れた道に迷ってしまった」、「よく会っている人なのに名前が出てこない」、など明らかに昔より物忘れが激しくなってきたとご自身では十分心当たりがあるにも関わらず「知人や家族に知られたくない」、「歳だからしょうがない」などと言ってごまかし続け、家族も親のそんな姿を見たくない事もあり、お互い認知症を“確定”するような診断には後ろ向きになりがちです。
先述の紹介した簡易的な認知症のテスターは一人でこっそり数分の手軽さで、しかも無料でできるアプリにとなるため、”診断する“といった重々しさもなくカジュアルに行えて、認知機能の現在地を確認し、専門医への受診の心構えにもなる良いツールであると感じました。

診断精度がすごい、AI診断による初期症状の”検出“
最新のAI診断による認知症の初期症状検出は、従来の医療診断を根本的に変革する革新的なアプローチとして注目されています。
その核心は、高度な機械学習アルゴリズムによる極めて精密な生体信号と認知機能の分析にあります。
初期症状の検出は、主に以下の複合的な方法によって実現されます:
1. 脳画像の精密分析
AIシステムは、磁気共鳴画像(MRI)や陽電子放射断層撮影(PET)などの脳画像を、ディープラーニングアルゴリズムによって、海馬の体積変化、脳組織の微細な構造変化、アミロイドプラークの蓄積などを、従来の診断方法では検出困難な初期段階で特定できます。
2. 認知機能テストのパターン認識
従来の認知機能テストをAIが高度に分析し、わずかな性能低下や反応時間の変化を検出します。機械学習モデルは、記憶力、注意力、言語機能などの複数の認知領域における微細な変化を統合的に評価し、初期段階の認知機能低下を予測します。
3. 多角的データ統合
遺伝的情報、血液検査結果、生活習慣データ、家族歴などを総合的に分析します。
これにより、単一の指標では捉えきれない複合的なリスク要因を考慮した、包括的な初期症状検出が可能になります。
4. 経時的変化の追跡
AIシステムは、同一患者の複数回の検査データを継続的に比較・分析し、認知機能の経時的な変化を高精度で追跡します。
わずかな変化のトレンドを検出し、認知症発症のリスクを早期に予測できます。
また、従来の年1-2回の健診に比べ、AI技術は日常的かつ負担の少ない方法で認知機能を継続的に評価でき、スマートフォンアプリや簡易テストを通じて、患者に過度な負担をかけることなく、定期的なスクリーニングを実現します。
5. 予測モデルの構築
機械学習アルゴリズムは、収集されたデータから個人に特化した認知症発症リスクモデルを構築します。
遺伝的要因、生活習慣、既往歴などを総合的に分析し、将来的な認知機能低下の可能性を予測します。
これらの技術的アプローチにより、AIシステムは従来の診断方法では見逃されがちだった初期症状を、驚くべき精度で検出することができます。単なる技術革新を超えて、認知症の早期発見と予防に革新的な可能性をもたらしているのです。
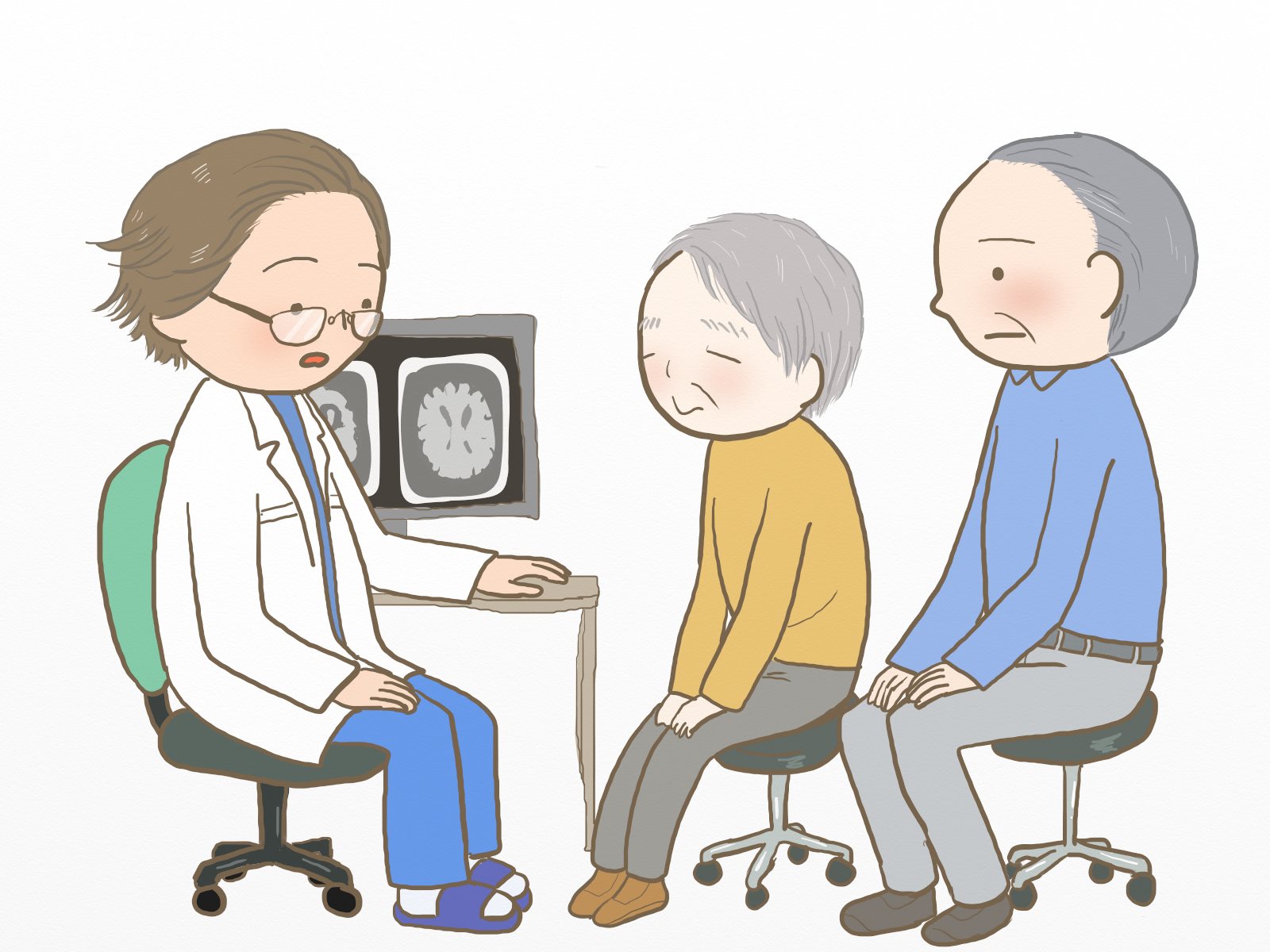
発展著しい、"遠隔診断”
診断精度もさることながら、受診のハードルを下げる、定期モニタリングの徹底などの目的で、従来の対面診療の制約を超え、遠隔診断の可能性が劇的に拡大しているといいます。
スマートフォン、ウェアラブルデバイス、IoT機器などを通じて、患者の認知機能を継続的かつ非侵襲的に評価することが可能になっており、日常的な認知機能テスト、行動パターン分析、生理学的データの収集を実現しています。
具体的な遠隔診断技術には、以下のようなアプローチがあります:
1. スマートデバイスによる認知機能評価
先述のような専用アプリケーションを通じて、記憶力、注意力、言語機能などを定期的にテストし、AIアルゴリズムが即座に分析します。反応時間、正確性、パターンの変化を追跡し、認知機能の微細な変化を検出します。
2. 遠隔画像診断
クラウドベースの医療画像プラットフォームにより、MRIや CT スキャンを遠隔で分析できます。AIシステムは、脳構造の変化や異常を高精度で検出し、専門医と瞬時に共有することができます。
3. 継続的データ収集と予測分析
ウェアラブルデバイスからリアルタイムで収集されるデータを、AIが継続的に分析。睡眠パターン、日常的な活動、生理学的変化などを総合的に評価し、認知症リスクを予測します。
遠隔診断の進化により認知症の簡易診断から専門医への受診、処方薬の手配とその後の進行のモニタリングなど一気通貫で行え、腰の重い高齢者でも自宅で手軽に、その気になれば家族にも詳細を知られることなく行う事が可能になります。
この夏、久しぶりに帰省した際に親の”取り繕い“を感じた方は是非、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?

その他のコラム
もっと見る











