どうなる⁈ 激増するシニアの“起業”
番号 55

嫌な思いをしてまで雇われ続けるなら、培った経験で起業を
先日、シニアの起業が急増している事例を目にしました。
70代の元エンジアの男性は、地域の農業を革新的なITソリューションで支援する起業を始め、農業用センサーとAIを活用した栽培支援システムを開発し、地域の若手農業者に技術指導を行い、男性の技術的知見が地域経済に直接貢献する先進的な事例として紹介されていました。
他にも、68歳の元小学校教諭の女性が、不登校の子どもたちのための学習支援コミュニティを立ち上げた事例が紹介されていました。
長年の教育経験を活かし、個々の子どもに寄り添った学習支援と心のケアを提供し、ボランティアの枠を超えて社会的包摂の重要な取り組みとして機能していました。
中小企業庁の調査によると、60歳以上の起業家の割合は近年急速に増加しており、2020年には起業者全体の約15%を占めるまでに至っているといいます。
また、起業の動機も多様化しており、総務省の調査によれば、起業した高齢者の約60%が「自己実現」または「社会貢献」を主な動機として挙げており、従来の退職後のライフスタイルが大きく変化してきていることがうかがえます。
年齢別の起業率を見ると、60〜65歳の層が最も起業活動が活発で、全体の約40%を占めているそうです。
また業態的には、サービス業、コンサルティング、小売業が上位を占めているといい、特に経営コンサルタントなど、豊富な経験と専門知識を活かした起業が目立つといいます。
さらに、起業後3年以上継続する割合も、若年層と比較して高く、約70%が安定した事業運営を実現しているといいます。
仕事で長く築き上げた人脈やリレーションを使い、自分が得意な小規模なマーケットの中で自身の生活分だけでも稼げれば…と"手狭"に"欲張らず"に少額の投資で営業することが安定経営のポイントとなっているといえます。
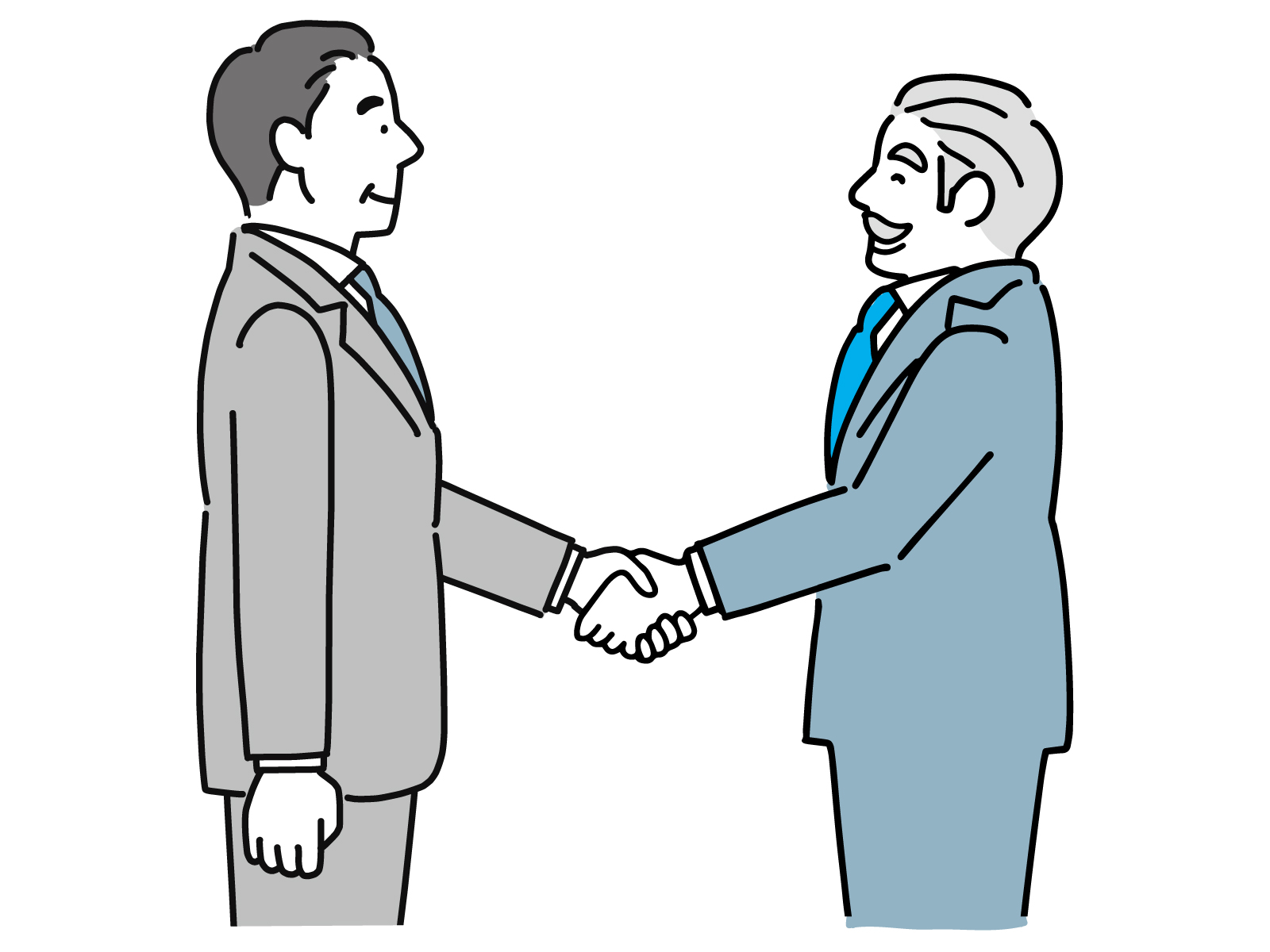
若い人に苦手な“大局観”
60歳以上の男女別の就業状況を見ると、男性の場合、就業者の割合は、60~64歳で83.9%、65~69歳で61.0%となっており、65歳を過ぎても、多くの人が就業しています。
また、女性の就業者の割合は、60~64歳で62.7%、65~69歳で41.3%となっています。
非正規の職員・従業員の比率を見ると、男性で60歳以降34%も上昇することから、
「まだまだ働く事はできるが、会社に期限付きの非正規で雇用され続けるより、ご自身の経験や知見を活かして自由に働きたい」
と考えるシニアが増えているのでは?と思います。
以下に、高齢者の起業に適した代表的なビジネスモデル例をご紹介します。
1.コンサルティング・サービス長年培ってきた専門知識と経験を活かし、特定の業界や分野でコンサルティングサービスを提供するモデル。
例えば、元経営者による中小企業経営コンサルティング、元教育関係者による教育戦略コンサルティング、退職した技術者による技術アドバイザリーなどが考えられます。これらのサービスは、比較的低投資で開始でき、柔軟な働き方が可能です。
2.オンライン教育・スキル伝承プラットフォームデジタル技術を活用し、自身の専門知識をオンライン講座や動画コンテンツとして提供するビジネスモデル。Zoomやオンライン学習プラットフォームを通じて、特定のスキルや経験を次世代に伝承することができます。語学、ビジネススキル、趣味の技術など、幅広い分野で展開可能です。
3.地域密着型サービス地域の特性や高齢者の生活に密着したサービスビジネス。例えば、地域の子育て支援、高齢者向けケア、地域の観光ガイド、地域特産品の販売など、地域社会のニーズに応えるビジネスモデルが考えられます。これらは、高齢者の豊富な地域知識と人脈を活かせる領域です。
4.クラフト・ハンドメイド事業手工芸品の製作・販売。オンラインマーケットプレイス(Etsy等)を通じて、世界中の顧客に独自の手作り製品を販売できます。陶芸、木工、織物、アクセサリー製作など、趣味を収益化できる可能性があります。
シニア向けビジネスサポート高齢者の視点から、他の高齢者向けのビジネスをサポートするモデル。高齢者向けのウェブサイト制作、デジタル機器サポート、起業支援コンサルティングなど、同世代のニーズを熟知している強みを活かせます。
これらのビジネスモデルは、高齢者起業家が持つ独自の強みを活かし、社会的価値を創出しながら、柔軟で持続可能な起業の道を開く可能性を秘めています。
重要なのは、個々の経験と情熱に基づいたモデルを選択し、継続的に学習とイノベーションに取り組むことだと考えます。

高齢者向け『起業支援プラン』
とはいえ、独立起業するにしても若年層よりハードルが高いのが現実です。
資金調達、デジタル技術の習得、健康面での制約、ビジネスの継続性など、高齢者起業家が直面する障壁は少なくありません。
これらの課題に対して、より包括的な支援体制の構築が求められています。
特に資金面については多くの銀行が、健康面やビジネスの信用性、担保など総合的に勘案し、長期的な事業継続性に疑問を抱き、起業に必要な初期投資資金の提供を躊躇する傾向にあります。
そういった意味では、もしも高齢者の起業が今後も加速するようであれば、高齢起業家向けの特別低金利融資制度の創設が求められます。
従来の制約を緩和し、事業計画の独自性と実現可能性に焦点を当てた審査システムへの転換が必要だと考えます。
シニア層の起業を支援するための補助金や助成金は、以下のようなプログラムが用意されています。
具体的な申請方法や条件については、各制度の公式サイトを確認するか、専門機関に相談することをお勧めします。
1. 創業補助金:新たに事業を始める際に支給される補助金で、一定の条件を満たすことで申請可能です。
2. 中小企業庁の助成金:中小企業を対象とした助成金制度があり、シニア起業者も対象になることがあります。
3. 地域の支援制度:各地方自治体でもシニア起業を支援するための助成金や補助制度が存在します。地域ごとに異なるため、地元の商工会議所や行政のホームページを確認することが重要です。
4. 専門機関の支援:日本政策金融公庫や各種のビジネス支援団体も、シニア層向けの融資や支援プログラムを提供しています。

高齢者の経済的自立は社会全体のメリット
高齢者の起業支援は、単なる経済的支援を超えた、包括的な社会的意義を持っています。
経済的自立の促進は、高齢者個人の生活の質を向上させるだけでなく、社会全体に重要な影響を与えます。
起業による経済的自立の最も顕著な効果は、高齢者の経済的依存からの脱却です。
従来の年金中心の生活モデルから、能動的に収入を得るモデルへの転換は、高齢者の経済的選択肢を大きく広げます。
総務省の調査によれば、起業した高齢者の約75%が、従来の年金収入に比べて安定的かつ高い収入を得ていることが明らかになっています。
経済的自立は、高齢者の自尊心と生きがいをもたらし、心理的側面にも重大な影響を与えます。
経済的な不安から解放され、自己実現の機会を得ることで、高齢者は社会のアクティブな構成員としての役割を再認識できるのです。
起業支援による経済的自立は、個人の生活改善だけでなく、社会保障システムにもポジティブな影響を及ぼします。
高齢者が経済的に自立することで、社会保障費の削減や、地域経済の活性化につながります。特に、地域密着型のビジネスモデルは、地域経済に直接的な貢献をもたらします。
具体的な経済効果として、以下のような側面が挙げられます:
・個人の追加収入創出
・社会保障費の間接的な削減
・地域経済の活性化
・高齢者の消費活動の拡大
・新たな雇用創出の可能性
特に、高齢者の消費活動は現在でも、106兆円と言われていますので、起業によってさらに加速されていけば、それだけでも経済効果に大きなインパクトをもたらす事が期待されています。
重要なのは、経済的自立が高齢者に単なる経済的恩恵だけでなく、社会参加の機会、自己実現、そして尊厳をもたらすことです。
アクティブシニアと言われる一つの要素として、こういったバイタリティを持っているかどうかも重要なアプローチといえます。
今後の展望として、高齢者起業支援は、単なる高齢者政策を超えた、社会全体の構造的変革につながる可能性を秘めています。
多様な世代が共存し、互いの強みを活かし合える柔軟な社会システムの実現が期待されます。
テクノロジーの進歩と高齢者の適応力が融合することで、新たな形の社会参加と価値創造が可能となるでしょう。
最終的に、高齢者起業支援は、高齢者個人の可能性を広げるだけでなく、社会全体の活力と持続可能性を高める戦略的投資なのです。
年齢に関わらず、個人の能力と意欲が尊重される社会の実現に向けて、継続的な取り組みが求められています。
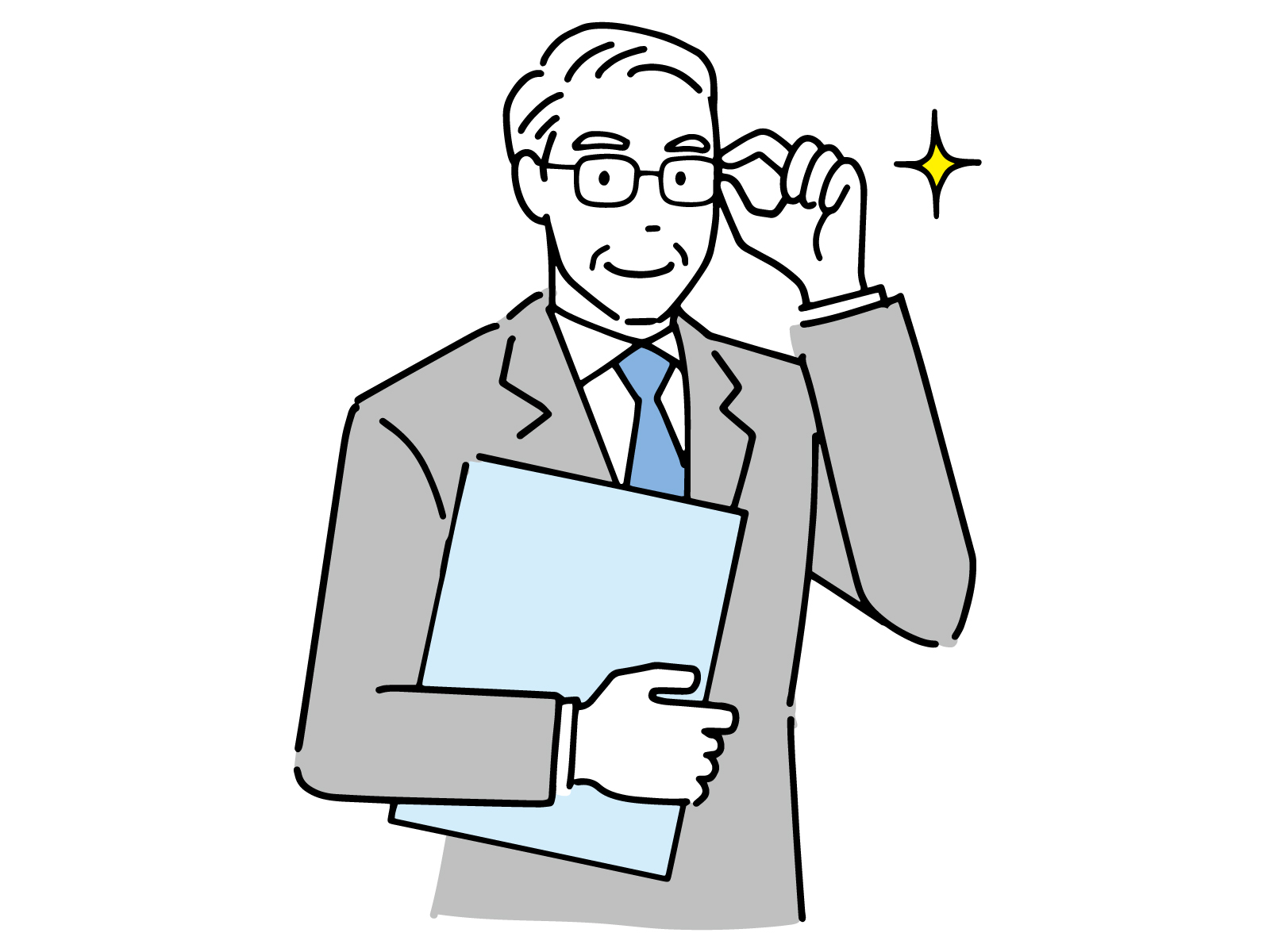
その他のコラム
もっと見る











