いよいよ来月改正!『育児・介護休業法』改正はダブルケアラーの強い味方になるか⁈
番号 51

会社の目を気にせず権利を行使する事はできるのか??
先日、所属している会社で、来月からの『育児・介護休業法』の法改正に伴い、リモートワークや育児・介護休暇についての社内規定が大きく変わるという通知がありました。
勤務先は100人ちょっとの外資系の中小企業で、海外とのリモート会議も多いにも関わらず、リモートワーク“超”反対派が多く、育児や介護に費やしている時間は「生産性につながらない“ムダ”な時間」と切り捨て、リモート申請にも社長を含めた4次承認ぐらいまであるため、数週間前から申請をして説明を促され、ようやく承認してもらえるという、社員の中では『リモート1日で退職が1年早まる』と、キャリアを削ってまで挑む『リモート申請オーディション』と呼ばれた一大イベントとなっていました。
見事オーディションに受かったとしても、リモート当日は勤怠システムの出退勤の通知を部内全員に知らせ、そのままフルタイムでカメラオンという“強烈”な2次審査が待ち構えており、耐えきれなくなった優秀な"多能工"社員が次々と条件の良い企業に引き抜かれ、あっという間に現場が正常稼働しないという異常事態に陥りました。
あれだけ個人のリモートの生産性を高らかに叫んでいた会社が、一番生産性が上がらない結末になるという、コントのような顛末を迎えていました。
我々、中小・零細企業の社員は一人が抱える業務範囲や業務量はとてつもなく、一人でもリモートで生産性が下がったり、育休産休などに入ろうものなら、あらゆる箇所へのインパクトが計り知れない為、『育児介護休業法』など守らなければ・・・と重々分かっていながらも、会社は見て見ぬふりをしてきました。
「社員のワークライフバランスなど必要なし」と切り捨て、昭和から一切更新せず時が止まったままの福利厚生に加え、都心から1時間以上もの僻地にある勤務地には、ある程度の給料を出しても募集要項の時点で応募など当然来ず、なるべくして"慢性人材難"に陥っている現状です。
そんな昭和感満載な勤め先でしたが、大手外資系企業からヘッドハンティングした“敏腕人事”の指揮の元、今回の改正を機にリモート勤務やフレックス、介護育児休業規定など、"戦略的"に福利厚生を見直し、まさに社運を賭けた『慢性人材難脱出プロジェクト』を発動させたという運びになったのでした。
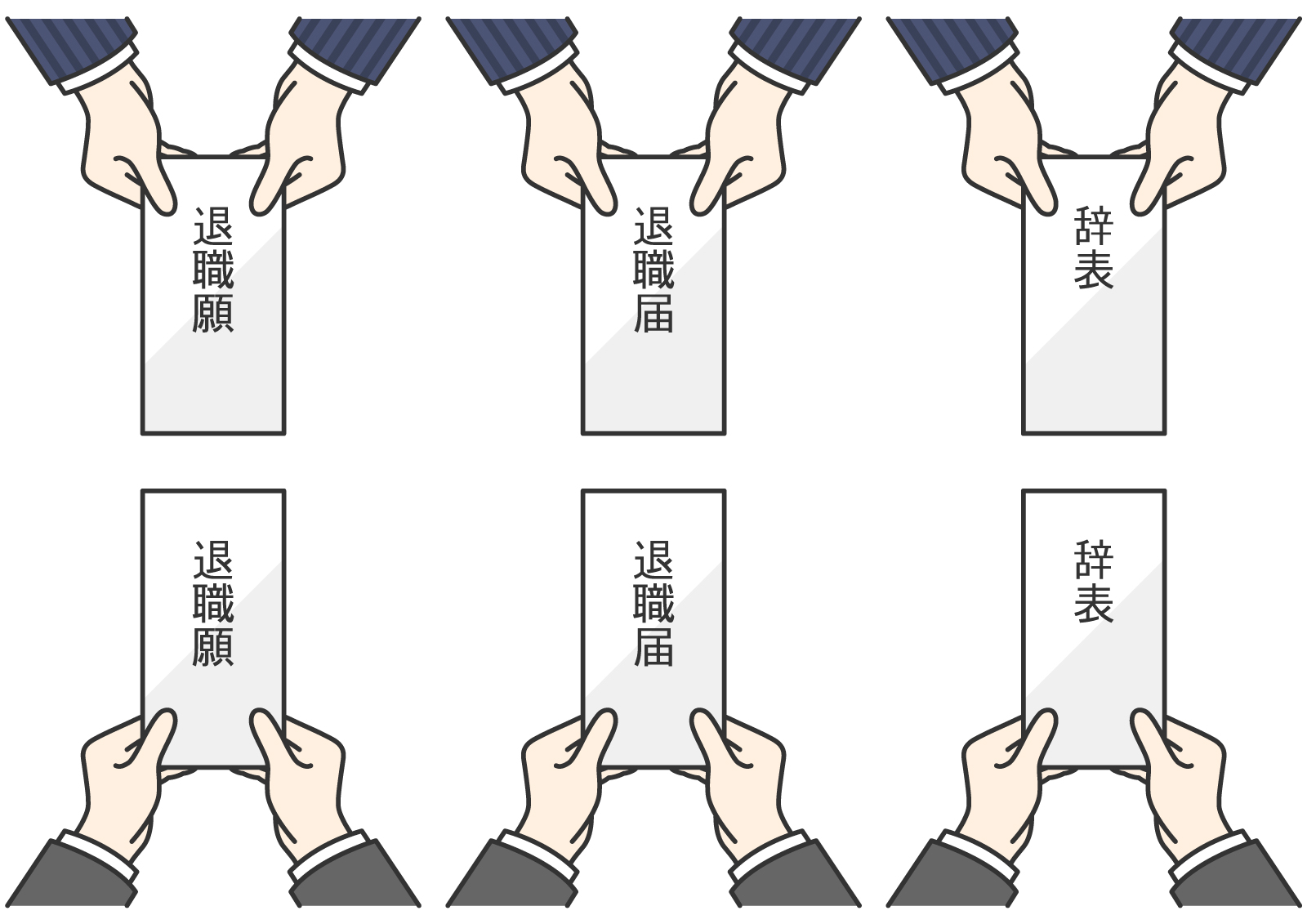
社員の“満足度”が企業へのロイヤリティ向上に変わる
今回の法改正は、2025年4月と10月に分けて改正され、従来の正社員中心の休業制度から、より包括的な労働者支援へと大きく転換します。
最も注目される変更点は、対象従業員の範囲を抜本的に拡大したことで、これまで主に正社員を対象としていた育児・介護休業制度が、パートタイム労働者、契約社員、派遣社員など、多様な雇用形態の労働者にも適用されるようになります。
また従来は大企業中心だった支援策でしたが、中小企業にも適用され、より多くの労働者にアクセス可能となる点が大きな改善ポイントとして挙げられ、まさに当社のプロジェクトのように、ダブルケアラーのワークライフバランスの実践は、生産性の向上、優秀な人材の確保と定着、イノベーション創出の能力など、組織の競争力を直接的に高める、絶好の『戦略的投資』機会であると捉えています。
昨今、従業員にとって、心身の健康、仕事への満足度、キャリア発展の機会が大幅に改善されており、特にミレニアル世代とZ世代の求職者は、給与水準だけでなく、職場環境の質と個人の生活の充実を重視する傾向が顕著です。
ある調査によると、約75%の若手キャリア人材が、ワークライフバランスを最優先の就職基準として挙げており、柔軟な働き方を提供する企業を強く選好しているといいます。
過度の労働ストレスや 『燃え尽き症候群』のような現象は、高度な専門性を持つ人材の離職を加速させる主要因であり、適切なバランス管理は人材流出を防ぐ効果的な戦略となります。
実際、ワークライフバランスに積極的な企業は、従業員の満足度が平均20%以上高く、離職率も大幅に低減できることが各種研究で示されています。
加えて、多様性と包摂性を重視する昨今の人材の価値観は、単に仕事の成果だけでなく、個人の成長と幸福を支援する企業を高く評価される傾向にあり、柔軟な働き方と心身の健康を支える環境は、優秀な人材にとって、その企業の先進性と人間中心のアプローチを示す重要な指標となっています。
この法改正により、中小企業にとって、業務調整や代替人員確保など、実務的な課題も存在するものの、単なる法的義務以上の戦略的意味を持ち、これらの課題を克服することで、より柔軟で競争力のある組織への変革が期待でき、限られた人的リソースの中で、従業員の仕事と家庭の両立を支援することは、人材定着と組織の生産性向上につながる重要な施策であることは、企業の大きさに限らず、もはや常識であるといえます。

過去10年で3倍、ダブルケアラーの"今"
育児休業法は1991年に、また介護休業法は2000年に施行され、改正が繰り返されてきました。
この法律によって、昨今では多くの男性が育休を取得したり、介護の為にフルリモート勤務をするなど、ダブルケアラーの働き方も常識も大きく変わったといえます。
2010年時点では、ダブルケアラーは年間約15万人程度と推計されていましたが、2020年には約45万人へと、実に3倍近くに増加しています。
この急激な増加の背景には、高齢化社会の進展と女性の社会進出が大きく影響しているといいます。
また、年齢層別の内訳では、特に40〜49歳の女性におけるダブルケアラーの割合が最も高く、全体の約60%を占めており、地域別では、特に大都市圏でその割合が顕著に高く、東京都、神奈川県、大阪府で全国平均を上回る傾向が見られるそうです。
さらに、興味深いのは、ダブルケアラーの就労状況の変化です。2015年以前は非正規雇用が多数を占めていましたが、近年では正規雇用のダブルケアラーの割合が増加しており、2022年時点では正規雇用が約45%に達しています。
女性の負担割合が高くなりがちな環境で、いかに優秀な女性社員の活躍をサポートし、キャリアの中断なく継続・復帰を促せるか?が今後のダブルケアラー活躍の“カギ”になっているといえます。

法改正のポイント
今回の法改正は、日本の家庭と労働環境に大きな変革をもたらす包括的な政策パッケージとして設計されています。
10月の改正分も含め、主な改正ポイントは以下の通りです
■育児支援に関する具体的な変更:
・子の看護休暇の見直し:これまで対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでだったのが、小学校3年生修了までに拡大
・両親の同時育児休業の拡大:父母がより柔軟に休業を取得できるよう、申請手続きと期間を緩和
・育児短時間勤務制度の拡充:短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
■介護支援における新たな施策:
・介護休業制度の再構築:介護を必要とする家族がいる労働者に対して、これまで原則連続取得とされていた介護休業を、通算93日の範囲内で休業を複数回に分けて取得可能に
・介護サービス利用への経済的支援の拡大:在宅介護や施設介護にかかる費用の一部を補助
・介護と仕事の両立支援:フレックスタイム制の拡大や在宅勤務の推進
また、特に大きく改正されたのは経済面での施策です。
介護や育児の経済的負担を実質的に軽減することで、包括的なアプローチを目的としています。
主な経済的メリットとしては以下のポイントが挙げられます。
■介護費用の一部負担軽減
介護費用軽減策の第一の柱は、介護保険の自己負担限度額の引き下げです。
従来、介護サービス利用時の自己負担割合は原則として1割または2割でしたが、今回の改正により、低所得世帯における自己負担割合を最大で0.5割まで引き下げます。
これにより、特に経済的に脆弱な世帯の介護費用負担が大幅に軽減されます。
第二に、介護休業取得時の所得保障も改善されます。
介護休業期間中の賃金補償率が現行の67%から80%に引き上げられ、介護に専念する家族の経済的リスクを軽減します。この措置により、介護と仕事の両立が容易になり、長期的な家計の安定にも寄与します。
さらに、多様な介護サービスへの経済的支援も拡大されます。
在宅介護サービス、短期入所サービス、デイサービスなどの利用に対する補助金が増額され、家族の選択肢が広がります。特に、中重度の介護を必要とする高齢者がいる世帯への支援が手厚くなっています。
■両立支援による就労所得の増加
次に両立支援策として、就労所得の増加に大きな可能性を秘めています。この改正の核心は、仕事と育児・介護の両立を可能にする柔軟な労働環境の創出にあります。
具体的には、フレックスタイム制の拡大と在宅勤務の推進が、特に子育て・介護中の労働者の就労継続を大きく支援します。
これまで仕事と家庭の両立が難しかった女性を中心に、労働市場への参加機会が拡大されることが期待されます。
例えば、短時間勤務制度の拡充により、週20〜30時間の柔軟な勤務が可能となり、家庭責任を果たしながら安定的な収入を得られるようになります。
特に女性の就労所得増加の観点から、この法改正は画期的で、育児休業の分割取得や、父母同時の育児休業取得が可能になることで、キャリアの中断リスクが大幅に軽減されます。これにより、女性の継続的な労働市場参加と、それに伴う所得の安定化が期待できます。
中小企業においても、これらの支援策が適用されることで、より多くの労働者が柔軟な働き方を選択できるようになり、推計によると、約30万人の女性が労働市場に新たに参入または継続就労できる可能性が見込まれています。
さらに、テレワークの制度化と支援により、地方在住者や育児・介護中の労働者の就労機会が拡大します。場所や時間に制約されない働き方は、潜在的な労働力の活用と、個人の就労所得の向上につながるでしょう。
これらの両立支援策は、単なる社会的支援を超えて、経済的な側面で重要な意味を持っています。柔軟な労働環境の整備は、個人の就労継続と所得向上を促進し、ひいては日本経済全体の生産性向上にも寄与すると考えられます。
■経済的メリット: 税制優遇措置
最後に税制優遇措置が挙げられます。子育て世帯向けの税制優遇は、特に多子世帯と中間所得層に焦点を当てています。
具体的には、18歳未満の子どもに対する追加的な所得控除枠が設けられ、第二子以降の子どもについては、年間最大36万円の税額控除が可能となります。
この措置により、子育て世帯の実質的な可処分所得が増加し、経済的負担が軽減されます。
介護家族に対する税制支援も大幅に拡充されます。介護休業取得者や在宅介護を行う家族に対して、最大50万円の特別税額控除が導入されます。
両立支援に関連する税制措置として、フレックスタイムや在宅勤務を活用する労働者に対する特別控除も創設されます。これにより、柔軟な働き方を選択する労働者の税負担が軽減され、仕事と家庭の両立を経済的側面から支援します。
これらの税制優遇措置は推計によると、対象となる世帯の平均で年間約20万円の実質的な税負担軽減が見込まる一方、効果的な実施には、適切な周知と柔軟な運用が不可欠であり、地方自治体や関連機関との緊密な連携により、すべての対象世帯が恩恵を受けられる仕組みづくりが求められます。

社内コミュニケーションも重視したい、『ハイブリットリモートワーク』
様々なメリットが享受できる可能性はある一方で、中小企業には業務調整や代替人員確保や育児・介護していない社員への公平感の配慮など、実践的な課題も存在します。
そんな背景もあり、最近では『ハイブリッドワーク』という働き方が、現代の労働環境における革新的なパラダイムシフトとして急速に台頭しています
多くの先進的企業では、従業員の自律性を尊重しながら、単なる一時的な対応策ではなく、デジタル時代の構造的な労働モデルとして、組織の目標と個人のワークライフバランスを両立させる新しいマネジメントアプローチを採用しています。
具体的な実装戦略としては、週2-3日のオフィス出勤と在宅勤務のローテーションが一般的になりつつあります。
ハイブリッドリモートを導入したある企業では、週に数日はオフィスで対面でのミーティングを行い、残りの日はリモートで集中して業務を進めるスタイルにした結果、チームのコミュニケーションが向上し、プロジェクトの効率が大幅にアップしたといいます
また、他のスタートアップ企業では、オフィスでの共同作業を重視し、クリエイティブなブレインストーミングセッションを行うことで、アイデアの質が向上し、リモート勤務の日には、個々が得意な作業に集中できる環境を整え、全体の生産性が向上しだという事例があります。
テクノロジーは、このトランスフォーメーションの重要な推進力となっています。
クラウドベースのコラボレーションツール、高度なビデオ会議システム、AIを活用したプロジェクト管理プラットフォームにより、物理的な距離を超えたシームレスな働き方が可能になっています。
セキュリティ技術の進化も、リモートワークの信頼性と安全性を大幅に向上させている。
将来的には、ハイブリッドワークはさらに進化し、より柔軟で個人最適化された働き方へと発展すると予想されます。
最終的に、ハイブリッドワークは単なる勤務形態の変更ではなく、組織文化の根本的な再構築を意味しています。
柔軟性、信頼、成果主義を重視する新しい価値観が、未来の働き方の新しいスタンダードとして確立されつつあります。
また、出勤と変わらない、またはそれ以上の生産性を確認するツールとしては、ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオ会議システムの他に、以下のような手法が登場しています。
【成果管理ツール例】
1.タスク管理ツール: TrelloやAsanaなどのパフォーマンスやプロジェクトを管理ツールを使用し、タスクの進捗状況を可視化します。
2. 時間追跡ソフトウェア: TogglやClockifyなどのツールを利用して、作業時間を記録し、業務の効率性を分析します。
3.キーロギング: キーボードの入力を記録するソフトウェアを使用することがありますが、プライバシーの観点から注意が必要です。

その他のコラム
もっと見る
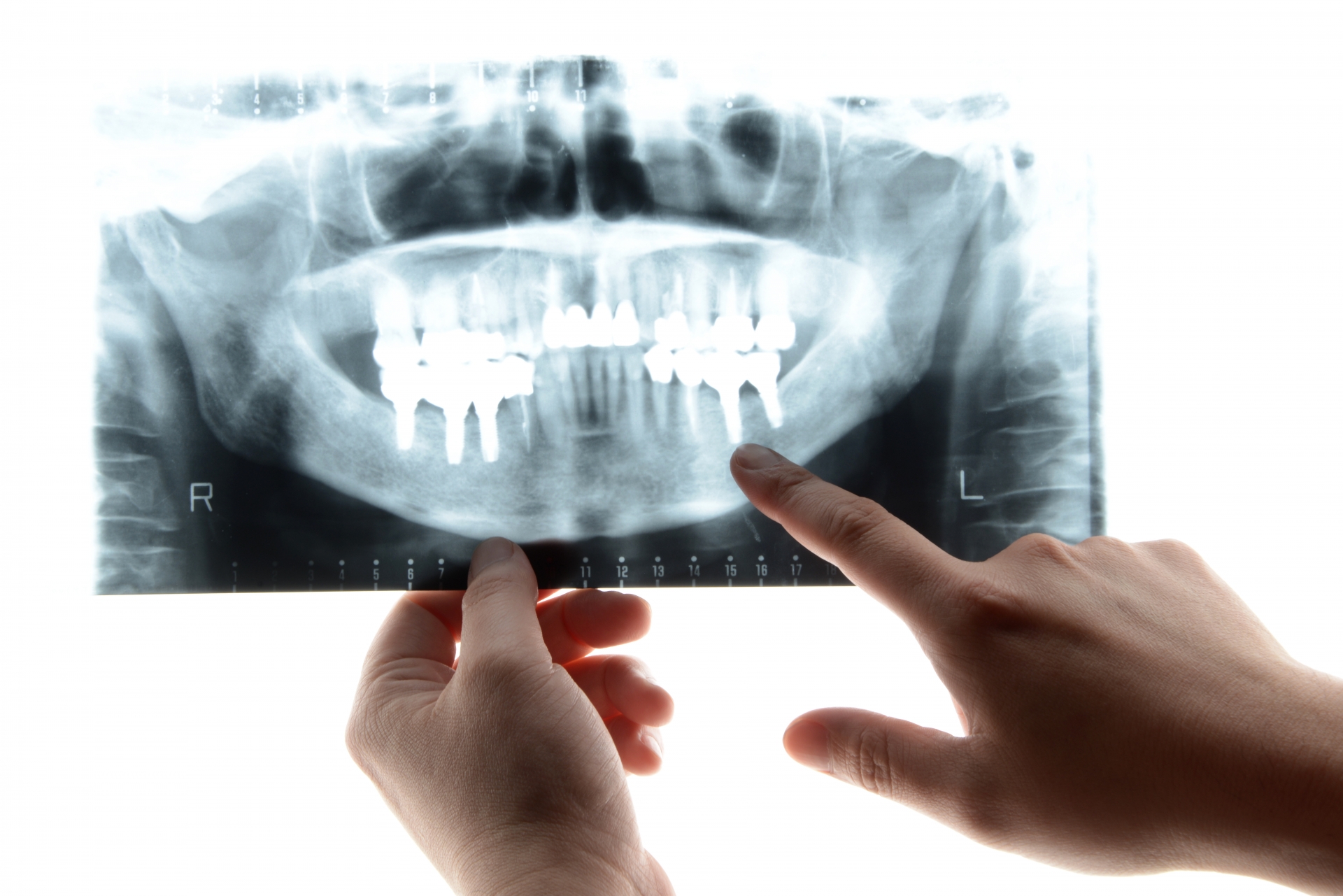
在宅とリモートで“診る”時代へ――AI画像診断が支える親介護の新常識
# 便利グッズ
# 介護録

親介護が“少し楽になる”VRの処方箋:在宅ケアを支える3つの転換 ――親介護の負担をVRで軽くする
# 便利グッズ
# 介護の準備

ユニマチュードが拓く“離職しない職場づくり”──認知症ケアの標準化で現場改革を実現する方法
# 制度
# 大切な家族へ

親介護の不安を減らす“免許返納という決断”——自転車すら使わせない「本当の安全」を考える
# 制度
# 大切な家族へ
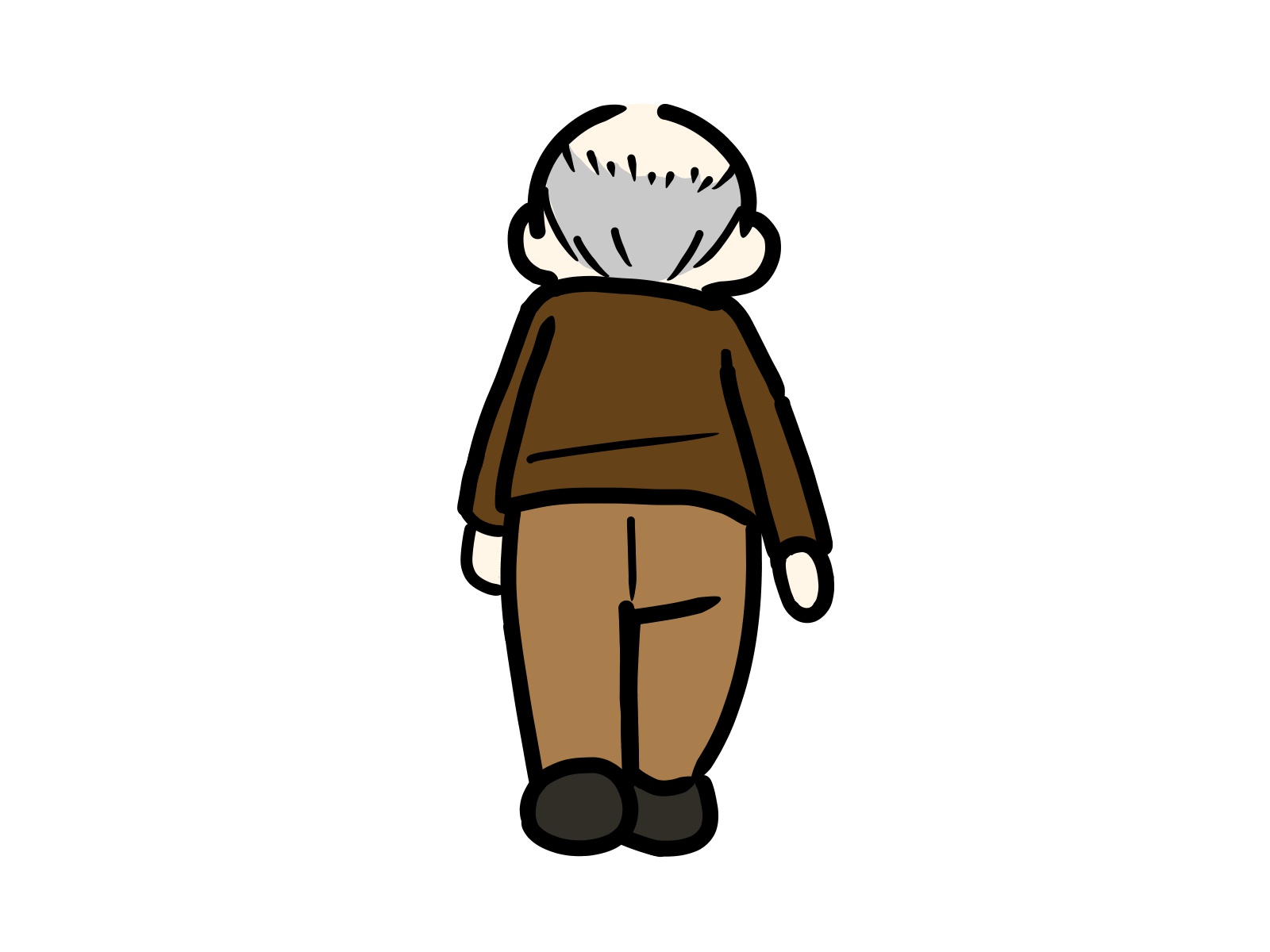
一生後悔する“どこへ?”を防ぎたい──親介護と最新デジタル徘徊防止機器で守る高齢者の命
# 便利グッズ
# 介護録
# 大切な家族へ






