親の認知症、放置しておくととんでもないことになってしまうかも… 介護家族への損害賠償実例
番号 47
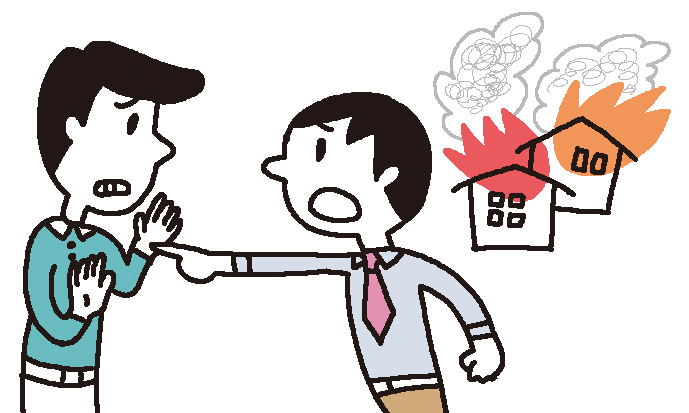
親が責任能力無くなってしまった場合、賠償するのは家族⁈
先日、栃木県宇都宮市が行っている“認知症事故救済事業”を紹介するページを見ました。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/koureisha/ninchisho/1032727.html
そこには、昨年2024年3月から開始し、認知症を原因とする事故により損害が発生した場合に、その補償に係る経済的負担を軽減するための『認知症事故救済制度』が紹介されていました。
市から要介護認定を受けており、何らかの認知症を有するが、ほぼ日常生活は自立している症状以上の方は自動加入となり、保険料も市が負担してくれるといいます。
また、補償の内容は法律上の賠償責任の有無に関わらず、事故の相手方に対して、死亡や怪我、物損などに係る給付金として最大3千万円まで支給され、保険加入者が賠償責任を負った場合に、身体賠償・財物賠償に係る保険金として最大2億円まで支給されるといいます。
この認知症事故救済制度は、「認知症施策推進法」という法律に基づき、法的な根拠も持ちつつ、国が定める「認知症施策推進大綱」に基づいて都道府県が中心となって運営しており、各自治体が制度の具体的な運用方法を定め、申請受付や支給決定を行っているようです。
お住まいの自治体によって取り組み度合いは変わりますが、実際の利用状況を見ると、全国で年間約10,000件の申請があり、そのうち8割程度が認定されているそうです。
また、制度の活用が進んでいる一方で、申請件数は認知症患者数に比べて極めて少ないのが現状で、制度の認知度が低いことや、申請手続きの煩雑さなど、利用者側の課題がまだまだ大きいことが原因と考えられています。
母も以前、介護施設で同じ入所者の方にケガをさせてしまい、損害賠償沙汰になる一歩手間まで発展してしまったケースもあった事から介護家族にとって“監督責任”がどこまで生じるのか?介護施設に入所していてもこういった制度は大いにチェックしておきたい所です。
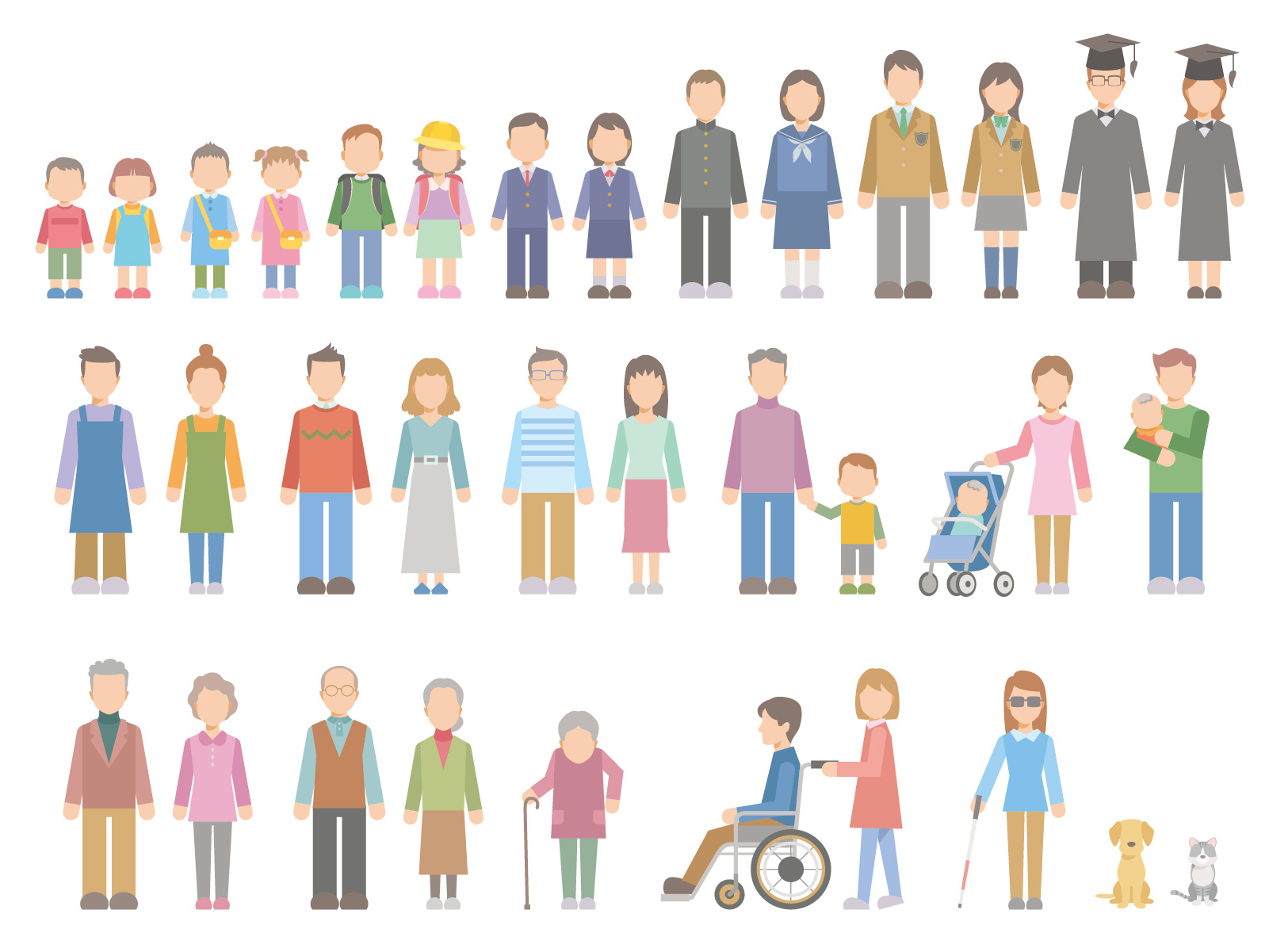
「私、関係ない」では済まされない 事例から見る認知症患者家族への賠償請求事例
基本的に認知症家族の監督義務者責任は、主に民法における監護義務に基づいているといいます。
この義務は、認知症高齢者の家族にも適用され、具体的には、認知症患者の家族は以下のような監督義務を負うと解されています。
1. 患者の行動を適切に管理し、第三者に対する危害や損害の発生を未然に防ぐこと。
2. 患者の生活環境を整え、必要な介護や医療サービスを確保すること。
3. 患者の財産管理や金銭管理を適切に行い、不正使用や詐欺被害などを防ぐこと。
4. 認知症の進行に伴う判断能力の低下に応じて、成年後見制度の活用など、適切な法的措置を講じること。
これらのことからも認知症患者が起こしたトラブルについては本人の責任能力が問えないこともあり、監督義務者である家族に対して損害賠償を請求されるケースが一般的です。
では、認知症家族が実際に損害賠償に至ったケースはどんなものがあるのでしょうか?
事例の一つ目は、東京都内の認知症高齢者施設において、患者が他の入居者を殴打し重傷を負わせた事件が発生しました。
この患者は家族が定期的に訪問し、見守りを行っていましたが、施設側の監視不足や対応の遅れも問題視されました。
結果、裁判所は家族の過失責任を認め、約300万円の損害賠償支払いを命じる判決を下したといいます。
他にも、埼玉県内の住宅街で、認知症の男性が徘徊中に歩行者にぶつかり重傷を負わせた事故が発生しました。
この男性の妻は認知症の進行に伴う行動障害への対応に苦慮していましたが、地域での見守りや支援が不足していたのが背景にありました。
裁判所は妻の過失責任を認め、治療費と慰謝料として約150万円の支払いを命じる判決を下しました。
一方で「家族に監督責任なし」という最高裁判決が出された事例もあります。
愛知県で重度の認知症の男性が同居する妻が目を離したスキに 1 人で外出し,鉄道の線路構内に立ち入って電車にはねられ死亡するという事故が発生しました。
この事故によって列車遅延等の損害をこうむった鉄道会社が,男性を監督する立場にある妻、および20年以上別居する長男を相手取って約720万円の損害賠償を請求する訴訟を提起し、上告審判決で最高裁判所は「夫婦の扶助の義務は抽象的なもの」として妻の監督義務を否定。
さらに、20年以上別居している長男についても監督義務者に当たる法的根拠はないとして、鉄道会社側の逆転敗訴が確定しました。
賠償金の支払いがなかったにせよ、ご家族が大きな裁判を起こされ、対応を余儀なくされたダメージは計り知れなく、生活すらままにならなかった事と思います。
ちなみに、この訴訟は、認知症患者が電車事故のような多くの人に影響を及ぼす甚大な事故を起こし、患者家族に多額の賠償が請求される事例として大きな話題となり、ある自治体では賠償金として最大3億円が支払われる保険に加入することを決めたそうです。

認知症の種類によっても行動特性は予測できる
認知症の種類によって特徴的な症状が現れ、事件や事故のリスクにつながっているといわれています。
例えば、アルツハイマー型認知症の患者が、記憶力の低下から自宅でガスの元栓を閉め忘れ、火災を引き起こした事例があります。
その方は時間や場所の見当がつかず、火災の危険性を認識できずに事態を悪化させてしまったそうです。
認知機能の低下が直接的な事故の原因となっている場合があります。
また、レビー小体型認知症の患者は、幻視や幻聴といった精神症状から、他人を攻撃的に威嚇する行動に及ぶことがあるため、患者は、周囲の人物を敵対的に捉え、危険な行為に走ることがあります。
認知症の高齢者を受け入れる介護施設でもチェックされている種類で、このような攻撃性の高まりは、患者の理解力の低下に起因するものと考えられています。
さらに、血管性認知症の患者は、実行機能の低下から、交通事故に巻き込まれるリスクが高いと言われています。
判断力の低下により、信号の意味が理解できずに、無謀な運転をする可能性があるとも指摘されています。
どんなに離れていても、どんなに疎遠になっていても親族である以上は“監督責任”を負うものだとされている一方で、高齢者の自己決定権は基本的人権の一つであり、認知症が進行しても可能な限り尊重されるべきとも主張されています。
家族としては極力トラブルを起こさないよう、十分な見守りを行っているつもりでも、強制的な監視や行動制限は、かえって高齢者のストレスを高め、心身の状態を悪化させるリスクがあります。
しかしながら、かつての強く、元気な姿を見てきた親が、意思疎通ができない、自分の事が自分でできないなど日に日に弱っていく姿に直面してきた時、子としてもそのギャップに大きなショックと多大なるストレスを抱え、かつてのように普通に接する事がもはや困難になる時は度々訪れます。
家族の健康状態悪化やバーンアウト、介護放棄・虐待のリスクなど最悪の状況を避けるため、公的な介護サービスの充実や地域包括ケアシステムの構築に加え、紹介したような制度などの社会的支援策の充実がさらに不可欠であると考えます。
そして今後、デジタル化がさらに進み、遠隔介護のような関節的なかかわり方によって介護家族の見守り方も大きく変化し、親の自己決定権と家族の心理的負担の良い折り合いがつくよう整備されていくことを願います。

その他のコラム
もっと見る











