「遠くの家族より近くのヘルパーさん⁈」各世代が“望む”介護環境とは?
番号 44
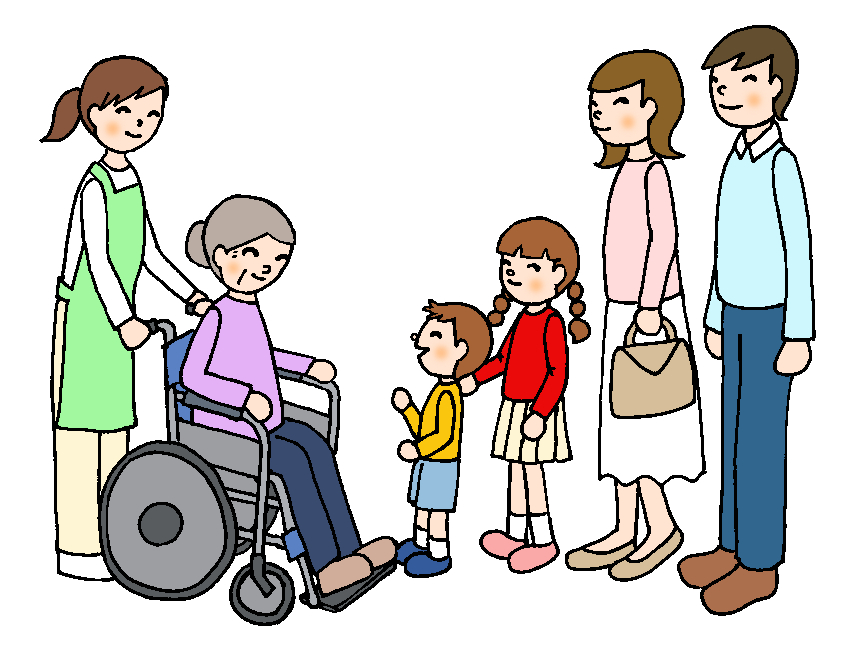
親の世話を「できない」のと「したくない」は大きく違う
先日、“終活”相談を行う会社の代表のインタビュー記事を目にする機会がありました。
そこには『“終活”相談者の9割は本人でなく息子や娘』という意外なコメントが載っていました。
さらに衝撃的だったのは『遠方で離れて暮らす親の支援を相談するのではなく、「すぐ近くに住んでいる親の面倒を見られない」という依頼が約6割に上る』というものでした。
元々、この会社は高齢者の終活のためのサービスでしたが、今では「親の面倒を見たくない、介護をしたくない」という子供世代からの相談のほうが多いといいます。
また、相談者は40代の一人っ子の単身男性が多く、その親は概ね70代で、厳しいしつけや干渉されすぎたという"毒親タイプ"のお子さんや、逆に育児放棄をされたようなお子さんと、両極端な家庭環境を経験された方々が多く、経済的に親の世話が『できない』というよりは、精神的に『したくない』という人が多いそうです。
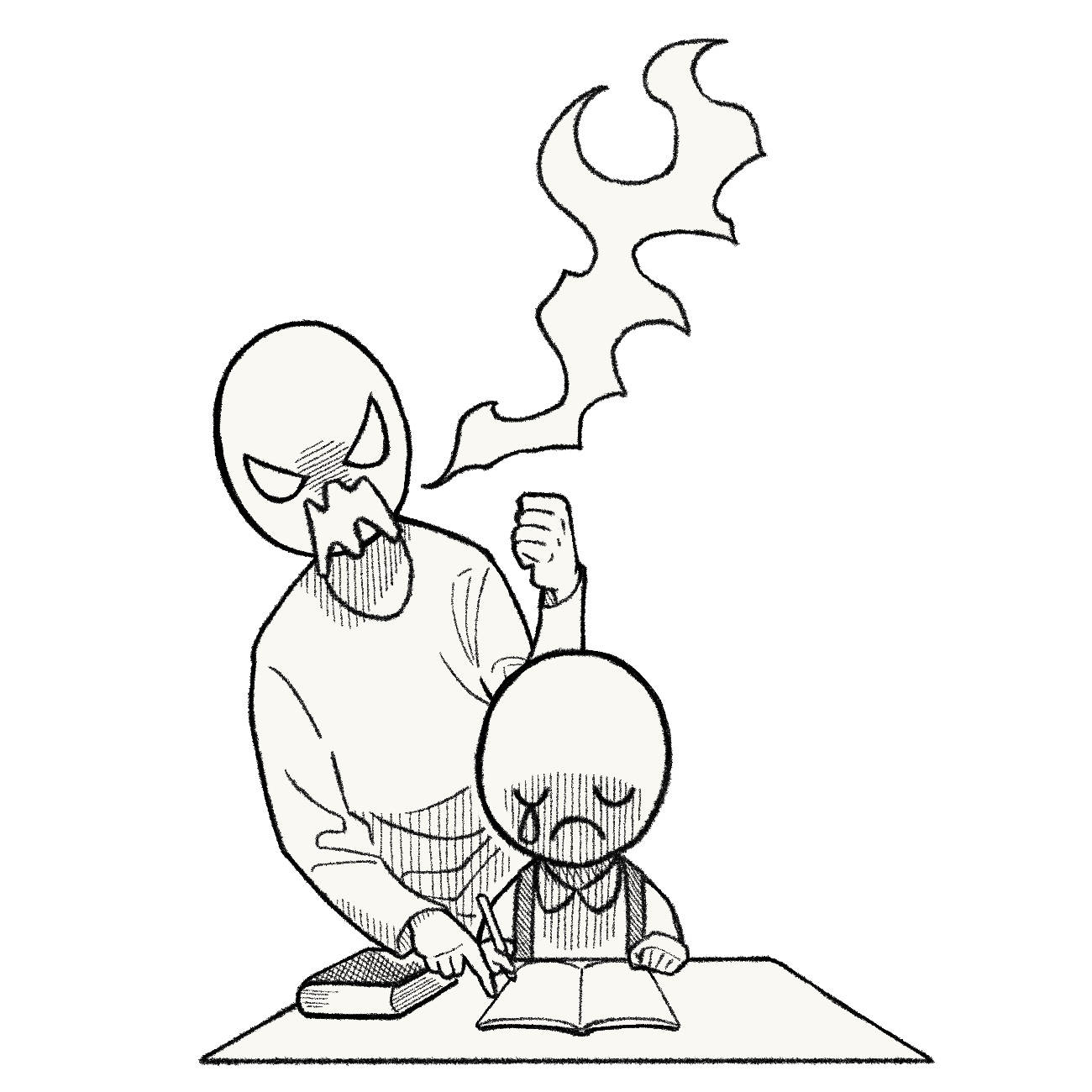
終活相談にどんな事を頼むのか?
こうしたニーズが爆増する背景には公的保険やサービスで賄えない“隙間”需要があると言います。
例えば、役所や病院の代行手続きや介護施設との窓口対応、認知症で迷子になった親の身元引受人として警察へ迎えに行き、さらに親が亡くなった時には、葬儀から火葬場、納骨の手配、場合によっては自宅の片付けまで頼まれるといいます。
中でも終活相談スタッフが一番躊躇する場面として、火葬場にも家族が誰も来ず、お骨を拾うことすらも代行したそうで、さすがに「本当に良いですか?」と火葬直前に依頼者へメールを打ったそうです。
また、費用感としても初期費用で50万円程度かかり、代行業務でも数千円~数万円と決して安くない時給が発生しますが、相談件数は1日数十件にも上り、この2年で売り上げは倍増したといいます。
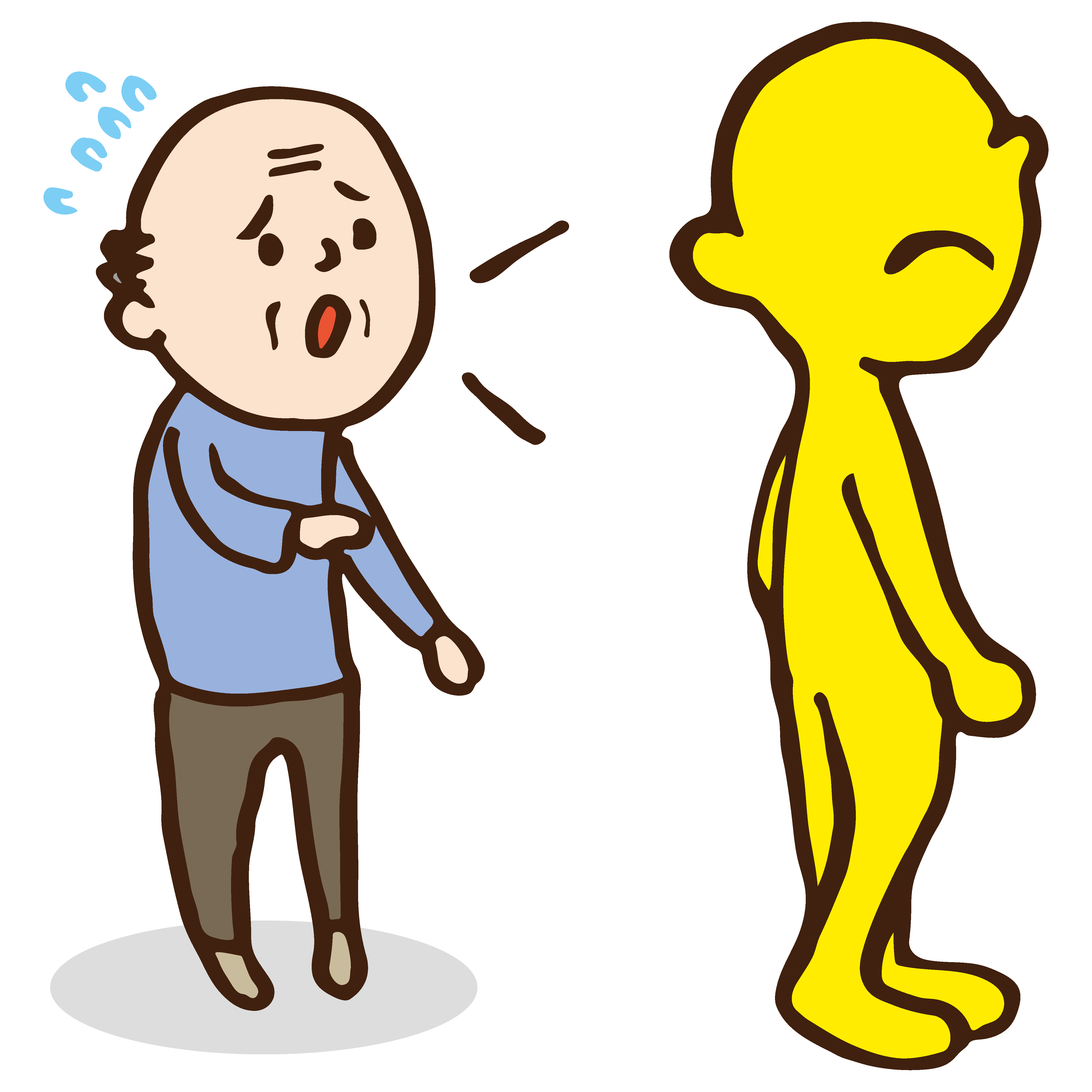
世代間による介護に対する意識
あるアンケート調査によると、以前は住み慣れた自宅で介護してもらいたいと90%近い高齢者が在宅介護を希望していましたが、最近では約6割程度になってきているといいます。
そんな背景を裏付けるかのように厚生労働省の調査によると、2025年には約300万人の高齢者が介護施設の入所を希望すると予測されており、2015年時点の約180万人から大幅に増加しているそうです。
また、施設介護を希望する高齢者は、「専門的なケアが受けられる」(55%)、「家族の負担を軽減できる」(47%)などを挙げ、さらには「自分の生活や健康状態を子供に見られたくない」といったプライバシーに関するものや「子供に頭を下げて負い目を感じたくない」など親としての自尊心やプライドを挙げたものもあるそうです。
一方で、子供世代での意識はどうかというと、子育てと両立する『ダブルケアラー』の中心的な世代である中年世代(40代~50代)は、「親の希望する介護方法を優先したい」(83%)、「家族で協力して介護したい」(72%)と回答した人が多数を占めたという結果になっています。
しかし、「仕事と介護の両立が大変」(75%)、「経済的な負担が大きい」(61%)と感じている人も多く、日常生活的にも経済的にも親があくまで“自分の事を自分でできる範囲”であれば親の意向をサポートする、といった意見が多数あったようです。
また、親の介護にはまだ直面する事が少ない若者世代(20代~30代)では、約6割が「介護施設やサービスを利用したい」と回答していました。
理由として、「仕事や家庭生活が忙しく、自宅での介護は難しい」(72%)、「経済的な負担が大きい」(68%)が挙げられ、「家族で協力して介護したい」と答えた割合は3割にとどまったといいます。
一見、前述したような親の終活を業者に“丸投げ”する事自体は人道的にも非情と思われがちですが、これらのアンケート回答を見ると、経済的なものさえ許せば、実は親と子双方にとって最も合理的で理想的な介護のカタチなのかもしれません。
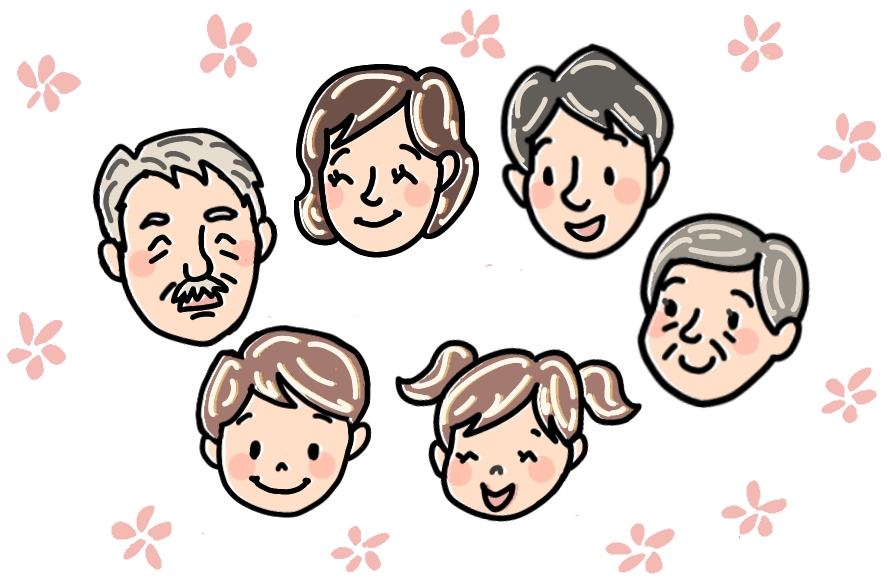
その他のコラム
もっと見る











